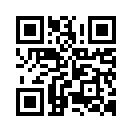グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
2014年05月01日
祝“高崎駅開業130周年”!!
祝“高崎駅開業130周年”!!

これじゃあ、「だるま弁当の街」です(笑)。
せめて、コレくらいは↓

高崎駅130周年記念弁当、26日発売 開業時の姿を掛け紙に 群馬
高崎弁当(末村歓也社長)は21日、「高崎駅開業一三〇周年記念弁当」を今月26日から発売すると発表した。
掛け紙は、明治17年5月の開業時、浮世絵師の栄斎重清(歌川重清)が描いた開花絵「上野高崎間鉄道之図」をセピア調にアレンジしたもの。同社はこの絵を保有しており、歴史を感じさせる演出に活用した。
記念弁当は人気の高い豚ショウガ焼きをベースに、ニンジンやダイコン、カボチャの煮物、高崎線をイメージした赤、緑、黄色のパプリカを配している。煮物に付けるタルタルソースと肉を2度楽しむ練りウメも添えた。
同駅の弁当売店で6月末まで販売。税込みで1個800円。
<引用:産経ニュース 2014.4.22 02:11>
ソース:http://sankei.jp.msn.com/region/news/140422/gnm14042202110001-n1.htm
>「高崎駅開業一三〇周年記念弁当」を今月26日から発売すると発表した。
なるほど・・・・・・
そういう事なんですね(^^ゞ
「高崎駅」
昭和四十五年、未だ「高崎駅」西口も停車場の趣をしていた。
駅舎は明治からの物だろうか白塗りの壁に年季の入った鴨居と頑丈そうなベンチには・・・・・
所謂「駅」と云う風情があった。
高崎駅の改札口は入り口と出口は別棟で何れも木戸に駅員が番を張っていた。
正面の大戸を入ると高い吹き抜けの天井、何かの絵画か彫刻があったように記憶するが、
それがなんであったか記憶は定かではない。
左手には「切符売場」があった。もちろんその時代のこと、自動切符販売機などは無い。
小窓に開いた向こうから、その時分は未だ「鉄道員」と云う、それは国家公務員・・・・・・
それが、如何にもといった面持ちで無愛想さを取り繕い極めて事務的に「お客さま」を捌いていた。
右手には待合室に売店。そこにはジュースの自動販売機などは無い。
もちろん缶入りのコーラや缶ジュースなどもだ。
新聞スタンドの脇に大きく「コカ・コーラ」と赤地に白抜きで横書きされた水冷式の冷蔵庫が・・・・・・
今に思えばそこに時代を映していた。
そして、アイスクリームの冷蔵庫も細長くその脇に並んでいて、
あの頃ちょいとした長旅にはそのアイスクリームの冷蔵庫に並べて入れられていた・・・・・
そう、あの小田原が発祥だという「冷凍ミカン」を必ず買ったのを覚えている。
待合室。
それは吹き抜けの正面玄関と冬場は大きな引き戸で仕切られていた。
正面の改札も今ほどの活況ではないが汽車を待つ客でそれなりに賑わい、
そのガラスの大戸の向こうには大きな石炭ストーブが勢いよく焚かれ待合客が暖を取っていた。
もちろん夏場にはエアコンなどと言うもの、当時は無かったのだが・・・・・
気を利かせた駅員が水うちをして涼を誘ってくれていた。
一番線のホームには上野からの電気機関車が「ゴー――ッ」とうねりを立てながら出入り、
夜の七時、八時ともなると金沢行きや秋田、青森行きの寝台夜行列車がホームを賑していた。
昭和の終り、六四年の頃に仕事でその一番線のプラットホームから・・・・・
寝台特急「いなほ」で青森まで行ったことが懐かしく思い出される。
今の、平成の高崎駅には残念ながらその趣はない。
まっ、「残念ながら」とは言ってもそれは僕だけの手前勝手なことなのかもしれないが、
今では「モントレー」とか何とか言うステーションビルにそれは味も塩ゃからけもなく変容してしまっている。
もちろんそこは北関東交通の要衝高崎、流行の珈琲専門ショップもぬかりがない。
「たかが珈琲、されど珈琲」とあつかましい。
因みに僕はその「珈琲」を一切やらないからどうでもいいんだが・・・・・・
それは「駅」という風情に欠ける、と思うのは僕の歳のせいかもしれない(笑)。
日本国有鉄道の都合かなんかは知らないが、かつての駅構内に「私が社長です」の大きな看板が。
それが、道行き人を見下ろしているのが薄ら可笑しい。
どうやら「駅前旅館」ならぬ「駅内ホテル」、さらに「駅内マンション」ときた日には言葉もない。
で、「高崎駅」と言えば、なんといっても「西口」、その趣だろう・・・・・・
「西口」は、駅舎を抜けると旅館、土産物屋が軒を並べ「万年屋」、「永楽」の食道に、
当時としてはずいぶんと繁盛した「ブリッジ」という2階建てのハイカラな駅前喫茶があった。
そして、レストラン喫茶「ナポリ」中心にした飲食街が駅前を賑やかにしていた。
で、駅前と言ったら「土産物屋」だろう、店の名前はなんと言ったか・・・・・
そうだ「堺屋土産物店」。駅を背中に右角にあったおみやげ屋。
そこの「南洋豆」という名前の南京豆菓子、不思議と美味くて事あるごとに買い求めていた。
二軒並んでいた手前の方の店である。
その頃はその飲食街の路地を通り抜けると南小学校辺りに夕方になると・・・・・
屋台の「おでんや」を商う店が未だ数件あったような記憶がある。
ほんのりとアルコールランプのともる「屋台」。グラスに注がれた日本酒か、焼酎の「梅割り」。
最後まで残っていたのは、四〇年代、その時既に70絡みの女将が、
その女将と、何を話すでもなくおでんを肴にコップ酒2、3杯ほろ酔い加減が赤城颪にはなんとも優しかった。
ところで、昭和四二年に「問屋町」なるものが仕上がるまでは高崎駅前通り・・・・・・
「吉野藤」、「国光」の老舗繊維問屋が新町の角に羽場を利かせていた。
「商都高崎」を象徴するが如く、駅前から立ち並ぶ旅館、土産物屋。
多分、岐阜、近江の繊維問屋が仕入れに卸にと忙しくしていたのだろう。
その屋号にはみんなこの高崎城下町の歴史を教えるその地方地方の名がつけられていた。
高崎の街にもモータリゼーションか、自動車の数も見る見るうちに増え・・・・・
そこで北関東初の問屋専門の街、「問屋町」が高崎の北部、飯塚と小八木をまたいで造られた。
商都高崎。その停車場から数歩に「豊田屋」、「信濃屋」の老舗旅館と、
その問屋筋「大店」の旦那衆の帳に料亭「岡源」さらには、元紺屋、中紺屋の繊維問屋街を過ぎれば、
「たかさき」の奥座敷、花街「柳川町」が袖を引かせた界隈が鎮座していた。
戦前、戦中、そして戦後と、所謂「青線」(因みに高崎は赤線ではないらしい)・・・・・・
それが芸子、妓娼を置いた「置屋」の町がそこには「大人の夜」を咲かせていたのだ。
昭和の戦前、大正ロマンと時代を遡ればまさに「ハイカラさんが通る」のそれだったと想像する。
時代は、軍靴のざわめきを他所に高崎の「モボ」、「モガ」といった、当時の「今の若いものは」が、
粋とお洒落を競ったのがその辺りだったのではないだろうか。
僕の祖父、明治半ば生まれの時代だろう。
そう、奇しくも「明治17年」申年生まれの僕の祖父、その年が高崎駅開業。
日清日露戦争、そして日中、太平洋戦争と艱難辛苦、幾多の歴史を超えてきた高崎駅だが・・・・・
さて、その「高崎駅」、そして「高崎」の今日はどうだろうか。
その「高崎駅」とともに発展してきたであろう、その高崎の街中だが、今は大きく変貌しようとしている。
「高崎駅」がゴージャスになればなるほど、その高崎駅「西口」、「東口」の賑わいを余所に、
「高崎の街中」がゴーストタウン化している、という現実をどう捉えるか・・・・・
ところで「機関車の街」高崎なんだが、機関車がどこにありますか???
せめて新橋の駅前広場みたいに「機関車」をという発送には至らないのでしょうか。
祝“高崎駅開業130周年”!!

これじゃあ、「だるま弁当の街」です(笑)。
せめて、コレくらいは↓

高崎駅130周年記念弁当、26日発売 開業時の姿を掛け紙に 群馬
高崎弁当(末村歓也社長)は21日、「高崎駅開業一三〇周年記念弁当」を今月26日から発売すると発表した。
掛け紙は、明治17年5月の開業時、浮世絵師の栄斎重清(歌川重清)が描いた開花絵「上野高崎間鉄道之図」をセピア調にアレンジしたもの。同社はこの絵を保有しており、歴史を感じさせる演出に活用した。
記念弁当は人気の高い豚ショウガ焼きをベースに、ニンジンやダイコン、カボチャの煮物、高崎線をイメージした赤、緑、黄色のパプリカを配している。煮物に付けるタルタルソースと肉を2度楽しむ練りウメも添えた。
同駅の弁当売店で6月末まで販売。税込みで1個800円。
<引用:産経ニュース 2014.4.22 02:11>
ソース:http://sankei.jp.msn.com/region/news/140422/gnm14042202110001-n1.htm
>「高崎駅開業一三〇周年記念弁当」を今月26日から発売すると発表した。
なるほど・・・・・・
そういう事なんですね(^^ゞ
「高崎駅」
昭和四十五年、未だ「高崎駅」西口も停車場の趣をしていた。
駅舎は明治からの物だろうか白塗りの壁に年季の入った鴨居と頑丈そうなベンチには・・・・・
所謂「駅」と云う風情があった。
高崎駅の改札口は入り口と出口は別棟で何れも木戸に駅員が番を張っていた。
正面の大戸を入ると高い吹き抜けの天井、何かの絵画か彫刻があったように記憶するが、
それがなんであったか記憶は定かではない。
左手には「切符売場」があった。もちろんその時代のこと、自動切符販売機などは無い。
小窓に開いた向こうから、その時分は未だ「鉄道員」と云う、それは国家公務員・・・・・・
それが、如何にもといった面持ちで無愛想さを取り繕い極めて事務的に「お客さま」を捌いていた。
右手には待合室に売店。そこにはジュースの自動販売機などは無い。
もちろん缶入りのコーラや缶ジュースなどもだ。
新聞スタンドの脇に大きく「コカ・コーラ」と赤地に白抜きで横書きされた水冷式の冷蔵庫が・・・・・・
今に思えばそこに時代を映していた。
そして、アイスクリームの冷蔵庫も細長くその脇に並んでいて、
あの頃ちょいとした長旅にはそのアイスクリームの冷蔵庫に並べて入れられていた・・・・・
そう、あの小田原が発祥だという「冷凍ミカン」を必ず買ったのを覚えている。
待合室。
それは吹き抜けの正面玄関と冬場は大きな引き戸で仕切られていた。
正面の改札も今ほどの活況ではないが汽車を待つ客でそれなりに賑わい、
そのガラスの大戸の向こうには大きな石炭ストーブが勢いよく焚かれ待合客が暖を取っていた。
もちろん夏場にはエアコンなどと言うもの、当時は無かったのだが・・・・・
気を利かせた駅員が水うちをして涼を誘ってくれていた。
一番線のホームには上野からの電気機関車が「ゴー――ッ」とうねりを立てながら出入り、
夜の七時、八時ともなると金沢行きや秋田、青森行きの寝台夜行列車がホームを賑していた。
昭和の終り、六四年の頃に仕事でその一番線のプラットホームから・・・・・
寝台特急「いなほ」で青森まで行ったことが懐かしく思い出される。
今の、平成の高崎駅には残念ながらその趣はない。
まっ、「残念ながら」とは言ってもそれは僕だけの手前勝手なことなのかもしれないが、
今では「モントレー」とか何とか言うステーションビルにそれは味も塩ゃからけもなく変容してしまっている。
もちろんそこは北関東交通の要衝高崎、流行の珈琲専門ショップもぬかりがない。
「たかが珈琲、されど珈琲」とあつかましい。
因みに僕はその「珈琲」を一切やらないからどうでもいいんだが・・・・・・
それは「駅」という風情に欠ける、と思うのは僕の歳のせいかもしれない(笑)。
日本国有鉄道の都合かなんかは知らないが、かつての駅構内に「私が社長です」の大きな看板が。
それが、道行き人を見下ろしているのが薄ら可笑しい。
どうやら「駅前旅館」ならぬ「駅内ホテル」、さらに「駅内マンション」ときた日には言葉もない。
で、「高崎駅」と言えば、なんといっても「西口」、その趣だろう・・・・・・
「西口」は、駅舎を抜けると旅館、土産物屋が軒を並べ「万年屋」、「永楽」の食道に、
当時としてはずいぶんと繁盛した「ブリッジ」という2階建てのハイカラな駅前喫茶があった。
そして、レストラン喫茶「ナポリ」中心にした飲食街が駅前を賑やかにしていた。
で、駅前と言ったら「土産物屋」だろう、店の名前はなんと言ったか・・・・・
そうだ「堺屋土産物店」。駅を背中に右角にあったおみやげ屋。
そこの「南洋豆」という名前の南京豆菓子、不思議と美味くて事あるごとに買い求めていた。
二軒並んでいた手前の方の店である。
その頃はその飲食街の路地を通り抜けると南小学校辺りに夕方になると・・・・・
屋台の「おでんや」を商う店が未だ数件あったような記憶がある。
ほんのりとアルコールランプのともる「屋台」。グラスに注がれた日本酒か、焼酎の「梅割り」。
最後まで残っていたのは、四〇年代、その時既に70絡みの女将が、
その女将と、何を話すでもなくおでんを肴にコップ酒2、3杯ほろ酔い加減が赤城颪にはなんとも優しかった。
ところで、昭和四二年に「問屋町」なるものが仕上がるまでは高崎駅前通り・・・・・・
「吉野藤」、「国光」の老舗繊維問屋が新町の角に羽場を利かせていた。
「商都高崎」を象徴するが如く、駅前から立ち並ぶ旅館、土産物屋。
多分、岐阜、近江の繊維問屋が仕入れに卸にと忙しくしていたのだろう。
その屋号にはみんなこの高崎城下町の歴史を教えるその地方地方の名がつけられていた。
高崎の街にもモータリゼーションか、自動車の数も見る見るうちに増え・・・・・
そこで北関東初の問屋専門の街、「問屋町」が高崎の北部、飯塚と小八木をまたいで造られた。
商都高崎。その停車場から数歩に「豊田屋」、「信濃屋」の老舗旅館と、
その問屋筋「大店」の旦那衆の帳に料亭「岡源」さらには、元紺屋、中紺屋の繊維問屋街を過ぎれば、
「たかさき」の奥座敷、花街「柳川町」が袖を引かせた界隈が鎮座していた。
戦前、戦中、そして戦後と、所謂「青線」(因みに高崎は赤線ではないらしい)・・・・・・
それが芸子、妓娼を置いた「置屋」の町がそこには「大人の夜」を咲かせていたのだ。
昭和の戦前、大正ロマンと時代を遡ればまさに「ハイカラさんが通る」のそれだったと想像する。
時代は、軍靴のざわめきを他所に高崎の「モボ」、「モガ」といった、当時の「今の若いものは」が、
粋とお洒落を競ったのがその辺りだったのではないだろうか。
僕の祖父、明治半ば生まれの時代だろう。
そう、奇しくも「明治17年」申年生まれの僕の祖父、その年が高崎駅開業。
日清日露戦争、そして日中、太平洋戦争と艱難辛苦、幾多の歴史を超えてきた高崎駅だが・・・・・
さて、その「高崎駅」、そして「高崎」の今日はどうだろうか。
その「高崎駅」とともに発展してきたであろう、その高崎の街中だが、今は大きく変貌しようとしている。
「高崎駅」がゴージャスになればなるほど、その高崎駅「西口」、「東口」の賑わいを余所に、
「高崎の街中」がゴーストタウン化している、という現実をどう捉えるか・・・・・
ところで「機関車の街」高崎なんだが、機関車がどこにありますか???
せめて新橋の駅前広場みたいに「機関車」をという発送には至らないのでしょうか。
祝“高崎駅開業130周年”!!
タグ :高崎駅、新橋駅、たか弁、だるま