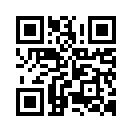グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
2013年07月20日
ガソリンが急騰の何故!??
ガソリンが急騰の何故!??
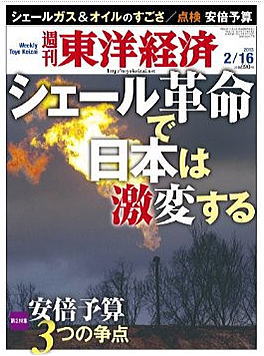
シェール革命で日本は激変する
ガソリン価格が急騰、レギュラー155.2円…前週から2.5円上昇
資源エネルギー庁が7月18日に発表した石油製品の店頭小売価格週次調査によると、7月16日時点でのレギュラーガソリンの全国平均価格は1リットル当たり155.2円となり、前週から2.5円上昇した。レギュラーガソリンの価格上昇は2週連続。
地域別では、北海道で3.3円、関東で2.9円、中国と東北で2.5円、中部と近畿で2.4円、九州・沖縄で2.0円、四国で1.7円と、全国すべての地域で大幅に上昇した。
ハイオクガソリンは2.5円プラスの166.0円、軽油は1.9円プラスの134.5円だった。
e燃費(運営:イード)によると、7月18日のレギュラーガソリンの全国平均価格は148.65円/リットル、ハイオクは160.02円/リットル、軽油は124.93円/リットルだった。
なお資源エネルギー庁による平均値は「販売」価格の平均であるのに対し、e燃費は「購入」価格の平均。現実の購入でユーザーは安い価格を指向するので、購入価格平均は販売価格平均より安くなる。
全国のガソリン価格平均推移、価格ランキングなどe燃費のデータは、燃費管理サイトの「カーライフナビ」で見ることができる。
<引用:response 2013年7月18日(木) 14時17分>
ソース:http://osigotosokuho.blog.fc2.com/blog-entry-952.html
高崎のガソリンスタンドでもこの2、3週間で・・・・・
セルフでリッターあたり「151円」と、
「141円」の表示、レギュラーガソリンが約10円急騰!!
まあ、円安、株高を喜んでいる日本の経済界だが、どうなんでしょう?
当然、政府調達の小麦等の穀物、食糧も「円安」で高騰している。
しかし、ホントに円安なのかが大いなる疑問だ、その意味ではボクらが現役世代は・・・・・
1ドル=120円前後の時代が長かったし、物価もそれなりに適正だったし、
所得も悪くはなかったが、今はどうだろう、低賃金、デフレ、そして「円安」はチョイとおかしい。
つまり、国民所得が十数年前の平均値よりも30%下落しているにもかかわらず、
「生活必需品」、とくに食料とエネルギーの価格が上昇を続ける。
まあ、一般大衆の関係のないところで「富の移動」が操作されるというのがホントのところか。
「株式」の世界なんてまさにそれで、一定のパイの中で「損得」が操作されているだけだし。
つまり、エネルギー資源にしてもそこでは生産調整され、その価格は操作される・・・・・
それが、戦争であったり、今の所は地域紛争とかだが(笑)。
まあ、僕らが小学生の頃のエネルギーといったら「石炭」オンリーだった。
学校のストーブも、「石炭室」っていうのがあってそこへバケツ片手に貰いに行く。
そして教室でダルマストーブにその石炭をくべて暖をとる・・・・・
もちろん、一般家庭では未だ石油ストーブなんてぇ時代じゃあないから「こたつ」。
そのコタツに、炭とか練炭とかを熾して、そのうち「豆炭アンカ」なるものが登場して、
そうそう、寝るときの湯たんぽも豆炭アンカに変わり、その意味では「エネルギー革命」だった。
ご飯を炊くにも風呂を沸かすにも「薪」から「ケンタ」、そして高級だった「炭」。
それがいつの間にか練炭、豆炭、それらが、まあ、今で言う横丁の「コンビニ」だった・・・・・
お米屋さん、そういえば雑穀を商う「油屋さん」なんてぇのもあって、
一般の家庭ではそういう店から一日に必要な分だけを買いに出かけていたもんだった。
まっ、そんな時代に、まさに「エネルギー革命」というか、そんな米屋さんとか雑穀屋さんとかが、
「灯油」なる、燃える水を販売し始めた。まさしくそれは「革命」だった。
当然それまでのコタツから石油スーブの普及、そうこうするうちに「燃える気体」・・・・・・
「プロパンガス」なるものが、まあ、当時はこの辺でも「東京ガス」、社会インフラは、
横丁のブルジョワジーのものでしかなかった庶民はもっぱら「プロパンガス」。
当然、それを商っていたのは「お米屋さん」とか「雑穀屋さん」で、
そうこうするうちに、調理用のプロパンガスコンロ、お風呂や給湯用のプロパンガス釜、
そういった「産業革命的」商品が一般家庭にも瞬く間に普及。
そのうちに、いわゆるモータリゼーション時代の到来が昭和40年代、一家に一台。
その頃になると町々の横丁に「ガソリンスタンド」なるものが立ちだした・・・・・
まあ、当時といえば戦後、その意味では未だ「20年」。平成を思い起こしてみれば、
今が「平成25年」だからそのことの凄さが想像できる。
1ドルが360円の固定相場制の時代で、まあ、需給バランスの関係なんだろうが、
僕が初めて「ガソリン」を車に入れた昭和42年、1リッター37円。
当時の高卒初任給が1万2千円前後だったから、つまり、初任給の3%チョイ・・・・・
エエッ!!今の高卒初任給って12万円チョイ、なんだ50年近い時間を費やして、
初任給、10倍にしかなっていない。
そういえば「高崎=東京」の国鉄運賃がたしか大人180円くらいだったような?
やはり、50年かけて約10倍の1890円!!
っと、思ったら日本てかなり物価安定な良い国でした(^^ゞ
昭和戦後史「たばことコーヒー一杯の値段」
ソース:http://shouwashi.com/transition-cigarette&coffee.html
国鉄、JR運賃くらいですねぇ10倍って・・・・・・
他はみんな5倍前後。
で、サラリーマン(世帯主)の平均月収が昭和40年代、約6万8千円。
平成5年のそれが約57万円だからまあ大体10倍・・・・・
でも、平成25年、新聞報道等によれば平均年収410万円!!(^^ゞ
つまり、平成5年から20年かけて200万円(3割)から平均下がってる。
で、アベノミクス、「10年間で国民所得を150万円上げる」って(笑)。
つまり、これから10年て、平成35年ですか???
それでも、平成5年を「取り戻せません」ね、まあ、国民総生産3%増とかですけど・・・・・・
物価は上昇気相ですね(^^ゞ
そう思うと、昭和40年代の政治家は偉かった、10年で約3倍超にしたんだから。
つまり、「所得」の「再配分」がネオコンっていうところでしょうか。
もちろん、安価なエネルギーがあったとしても既得権益の石油マフィアがそれを許さない。
昭和30年代には「炭管疑獄」なんてぇのもあった。
つまり、石炭マフィアの生死を賭けた戦いだったけど、敗れたのは炭鉱労働者だけ。
そのマフィアは「石炭」から「石油」にシフト、つまり、石油から新エネルギーへの移行。
つまり、国民消費者は永遠とその既得権益に搾り取られるだけ・・・・・
まあ、「ガソリンスタンド」も淘汰の時代ですから、誰も保障してくれない(^^ゞ
ガソリンが急騰の何故!??
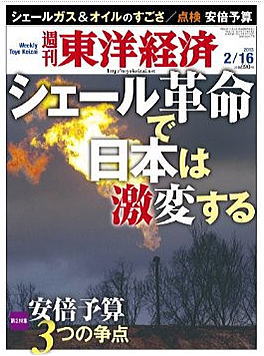
シェール革命で日本は激変する
ガソリン価格が急騰、レギュラー155.2円…前週から2.5円上昇
資源エネルギー庁が7月18日に発表した石油製品の店頭小売価格週次調査によると、7月16日時点でのレギュラーガソリンの全国平均価格は1リットル当たり155.2円となり、前週から2.5円上昇した。レギュラーガソリンの価格上昇は2週連続。
地域別では、北海道で3.3円、関東で2.9円、中国と東北で2.5円、中部と近畿で2.4円、九州・沖縄で2.0円、四国で1.7円と、全国すべての地域で大幅に上昇した。
ハイオクガソリンは2.5円プラスの166.0円、軽油は1.9円プラスの134.5円だった。
e燃費(運営:イード)によると、7月18日のレギュラーガソリンの全国平均価格は148.65円/リットル、ハイオクは160.02円/リットル、軽油は124.93円/リットルだった。
なお資源エネルギー庁による平均値は「販売」価格の平均であるのに対し、e燃費は「購入」価格の平均。現実の購入でユーザーは安い価格を指向するので、購入価格平均は販売価格平均より安くなる。
全国のガソリン価格平均推移、価格ランキングなどe燃費のデータは、燃費管理サイトの「カーライフナビ」で見ることができる。
<引用:response 2013年7月18日(木) 14時17分>
ソース:http://osigotosokuho.blog.fc2.com/blog-entry-952.html
高崎のガソリンスタンドでもこの2、3週間で・・・・・
セルフでリッターあたり「151円」と、
「141円」の表示、レギュラーガソリンが約10円急騰!!
まあ、円安、株高を喜んでいる日本の経済界だが、どうなんでしょう?
当然、政府調達の小麦等の穀物、食糧も「円安」で高騰している。
しかし、ホントに円安なのかが大いなる疑問だ、その意味ではボクらが現役世代は・・・・・
1ドル=120円前後の時代が長かったし、物価もそれなりに適正だったし、
所得も悪くはなかったが、今はどうだろう、低賃金、デフレ、そして「円安」はチョイとおかしい。
つまり、国民所得が十数年前の平均値よりも30%下落しているにもかかわらず、
「生活必需品」、とくに食料とエネルギーの価格が上昇を続ける。
まあ、一般大衆の関係のないところで「富の移動」が操作されるというのがホントのところか。
「株式」の世界なんてまさにそれで、一定のパイの中で「損得」が操作されているだけだし。
つまり、エネルギー資源にしてもそこでは生産調整され、その価格は操作される・・・・・
それが、戦争であったり、今の所は地域紛争とかだが(笑)。
まあ、僕らが小学生の頃のエネルギーといったら「石炭」オンリーだった。
学校のストーブも、「石炭室」っていうのがあってそこへバケツ片手に貰いに行く。
そして教室でダルマストーブにその石炭をくべて暖をとる・・・・・
もちろん、一般家庭では未だ石油ストーブなんてぇ時代じゃあないから「こたつ」。
そのコタツに、炭とか練炭とかを熾して、そのうち「豆炭アンカ」なるものが登場して、
そうそう、寝るときの湯たんぽも豆炭アンカに変わり、その意味では「エネルギー革命」だった。
ご飯を炊くにも風呂を沸かすにも「薪」から「ケンタ」、そして高級だった「炭」。
それがいつの間にか練炭、豆炭、それらが、まあ、今で言う横丁の「コンビニ」だった・・・・・
お米屋さん、そういえば雑穀を商う「油屋さん」なんてぇのもあって、
一般の家庭ではそういう店から一日に必要な分だけを買いに出かけていたもんだった。
まっ、そんな時代に、まさに「エネルギー革命」というか、そんな米屋さんとか雑穀屋さんとかが、
「灯油」なる、燃える水を販売し始めた。まさしくそれは「革命」だった。
当然それまでのコタツから石油スーブの普及、そうこうするうちに「燃える気体」・・・・・・
「プロパンガス」なるものが、まあ、当時はこの辺でも「東京ガス」、社会インフラは、
横丁のブルジョワジーのものでしかなかった庶民はもっぱら「プロパンガス」。
当然、それを商っていたのは「お米屋さん」とか「雑穀屋さん」で、
そうこうするうちに、調理用のプロパンガスコンロ、お風呂や給湯用のプロパンガス釜、
そういった「産業革命的」商品が一般家庭にも瞬く間に普及。
そのうちに、いわゆるモータリゼーション時代の到来が昭和40年代、一家に一台。
その頃になると町々の横丁に「ガソリンスタンド」なるものが立ちだした・・・・・
まあ、当時といえば戦後、その意味では未だ「20年」。平成を思い起こしてみれば、
今が「平成25年」だからそのことの凄さが想像できる。
1ドルが360円の固定相場制の時代で、まあ、需給バランスの関係なんだろうが、
僕が初めて「ガソリン」を車に入れた昭和42年、1リッター37円。
当時の高卒初任給が1万2千円前後だったから、つまり、初任給の3%チョイ・・・・・
エエッ!!今の高卒初任給って12万円チョイ、なんだ50年近い時間を費やして、
初任給、10倍にしかなっていない。
そういえば「高崎=東京」の国鉄運賃がたしか大人180円くらいだったような?
やはり、50年かけて約10倍の1890円!!
っと、思ったら日本てかなり物価安定な良い国でした(^^ゞ
昭和戦後史「たばことコーヒー一杯の値段」
ソース:http://shouwashi.com/transition-cigarette&coffee.html
国鉄、JR運賃くらいですねぇ10倍って・・・・・・
他はみんな5倍前後。
で、サラリーマン(世帯主)の平均月収が昭和40年代、約6万8千円。
平成5年のそれが約57万円だからまあ大体10倍・・・・・
でも、平成25年、新聞報道等によれば平均年収410万円!!(^^ゞ
つまり、平成5年から20年かけて200万円(3割)から平均下がってる。
で、アベノミクス、「10年間で国民所得を150万円上げる」って(笑)。
つまり、これから10年て、平成35年ですか???
それでも、平成5年を「取り戻せません」ね、まあ、国民総生産3%増とかですけど・・・・・・
物価は上昇気相ですね(^^ゞ
そう思うと、昭和40年代の政治家は偉かった、10年で約3倍超にしたんだから。
つまり、「所得」の「再配分」がネオコンっていうところでしょうか。
もちろん、安価なエネルギーがあったとしても既得権益の石油マフィアがそれを許さない。
昭和30年代には「炭管疑獄」なんてぇのもあった。
つまり、石炭マフィアの生死を賭けた戦いだったけど、敗れたのは炭鉱労働者だけ。
そのマフィアは「石炭」から「石油」にシフト、つまり、石油から新エネルギーへの移行。
つまり、国民消費者は永遠とその既得権益に搾り取られるだけ・・・・・
まあ、「ガソリンスタンド」も淘汰の時代ですから、誰も保障してくれない(^^ゞ
ガソリンが急騰の何故!??