2009年11月20日
馬跳び遊び・・・・・

僕らの小学校の頃の冬の遊びといえば、
「馬跳び」
Wikipediaとは少々ルールが違うかもしれない・・・・・・
確か敵味方に分かれて、大将が馬の首になって、数人で乗りかかってくる敵の殿とじゃんけんをして負けたら交代。
で、そのじゃんけん中に、馬になっているモノが数珠つなぎになったままその馬に乗っかったモノを揺り落とす・・・・・
落ちたらその敵の負け。しかし、馬が崩れたら馬チームの負け。
まあ、元気のいいガキ大将クラスとか、ムチャクチャ重たいのが「ドッスーーーン」と来ると、馬が崩れる(笑)。
とにかく、寒い冬です。当時は靴なんか履いている奴はまれで、ほとんどが下駄に足袋。
多分下駄は脱いで素足でやったんだと思う。危ないし・・・・・・
おしくらまんじゅう、押されて泣くな、
おしくらまんじゅう、押されて泣くな、
そのあとはなんだったっけかなぁ???
冬場の定番だったような「おしくらまんじゅう」・・・・・・
「ちず(地図)遊び」
校庭に地図というか、大きな道を描いて、その真ん中に「38度線」を引く・・・・・
で、その「38度線」で敵味方、交互に引っ張りっこをするんじゃあなかったかな?
で、最後に一人になっちゃった方が負け。
しかし、子どもの遊びにしては、「38度線」。そうなんです、あの頃ちょうど南北朝鮮の戦争も終わり、
今にして思えば、「板門店」、つまり「38度線」です。
アレは小学校4年?5年??
確かそんな頃だったけど、同級生に「崔くん」という在日の友だちがいて、
国の北朝鮮帰還事業でその「崔くん」が北朝鮮に帰ることになった。
詳しくは思い出せないが、そんなさ「崔くん」を送る会みたいなことをクラスでしたような記憶が・・・・・
「崔くん」、北朝鮮でどうしているんだろうか?
まあ、「ちず」っていう遊び、なかなか政治的な遊びですね(笑)。
「キンピョーごっこ」
アレは岸政権の時だったか、文部省の「教師の勤務評定」の法制化っていうのがあって・・・・・・
まあ、それに反対する先生が、
「勤評反対」。それを「キンピョー反対、キンピョー反対」のシュプレヒコールでデモをする。
まあ、ソレを真似て、悪ガキ連中が・・・・・・
「キンピョー反対、キンピラくいてえ」とかいって先生を怒らせた記憶が(笑)。
まあ、当時は遊びには事欠かなかった。
「三角ベース野球」、「ドッジボール」、「相撲ゴッコ」とか。
まっ、家に帰れば「メンコ」、「ビー玉」、「ベーゴマ」、つまり「勝負事」です。小学校の頃から(笑)。
で、メンコも油をしみこませて重ねて縫ったり、ベーゴマはヤスリで研いだり、近所の鉄鋼所のグラインダでへそを作ったり。
まあ、勝つための創意工夫ですね・・・・・・
横丁の悪ガキの遊びは、親には内緒の「川越え」。今の和田橋辺りのところを片岡の方へ渡る遊び。
で、「千人隠れ」へ行ったのはいつの頃のことだったろいうか・・・・・・
Posted by 昭和24歳
at 09:28
│Comments(4)
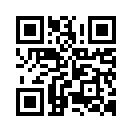


が、いまは「負けてかわいそう」だからと「勝負ごと」がどんどんとなくなっていき・・・
「負ける」ことに対する経験をつまないから、一度や二度の負けで立ち直れなくなるんですよね。
勝負ごと、どんどんすればいい。
勝っても負けても、その後のフォローが大切なんだから。
なんて、公園で遊んでいた最後の世代として、コメントしてみました。
そうですね。子どもの頃何度も何度負けて・・・・・
そして勝った時の喜び。
僕は腕力は強くなかったので、強いやつとどう接するか、またどう戦うか・・・・・
>「負ける」ことに対する経験をつまないから、一度や二度の負けで立ち直れなくなるんですよね。
仰るとおりです!!
「勝った喜び」は一様ですが・・・・・
「負けた悔しさ」はそれぞれです。
そこに智慧が生まれ、工夫が生まれます。
「キンピョーごっこ」は知りませんでした。
私の地域だけかな?
「石オニ」ってのがありました。
追いかけっこなんですが、石の上しか逃げたり追いかけたりできないんです。
その頃、高崎神社境内はほとんど土むき出しで、石は参道と石碑、お稲荷さんの岩屋、神殿の石玉垣くらいのもんでした。
おかげさまで、遊びながら敏捷性や筋力を付けられたと思ってます。
昨日は娘の子どもたちが来まして近くの公園に行きました。
「石オニ」でなくて、その子どもたちは「高オニ」とかで遊んでます。
木に登ったり、ブランコをしたり、2時間近く、途中ワングーでアイスを食べて・・・・
疲れを知らない子どもたちです。
ゲームをしている時より嬉々としてますね。
僕らの子ども時代はそんな集団遊びができましたけど・・・・・
少子化でしょうか、今はソレもかなわぬようです。しかし娘の3人子、寄ると触るとケンカです(笑)。