2009年11月13日
豊かさとは何か・・・・
豊かさとは何か・・・・

優しくない国は豊かではない Date:2009-09-05
<レビュー引用>
日本は経済大国であるというが豊かな国ではないと著者は言う。何故なら経済力が国民の生活の豊かさには結びついていないから。格差や不公正は拡大し、基本的人権さえ守られていない。勤労者は長い労働時間に疲れきっており、労働の果実は小さく、老後のケアは貧しい。本書は古いと言われ実際書かれたのはかなり昔であるが、告発されている多くの問題は現代にも通じているし、普遍的な問題意識とすら言ってもいい。
物や金の豊かさに没入する事を批判する向きはよくあるものだ。中には豊かさ批判を保守的な価値観の強要やパターナリズムに繋げてしまう人もいるが著者はあくまで多様な生き方、多様な価値観がある事を前提しつつ多様な人々の中にも、社会的にこのような条件があればそれぞれの人が豊かな人生を生きやすくなると考えられる共通の一致点があるはずだ、その共通部分を豊かにすべきではないか、という姿勢をとる。
<以下本文>
09年度の税収は40兆円を下回り、法人税収入は8兆円前後で、ピークだったバブル期、89年度(約19兆円)の半分に満たない水準に落ち込んでいる。
つまり、商売の利益からの税収が落ち込み、所得からの税収も落ち込み、イコール消費も落ち込み消費税収も落ち込む。
なにもかも「落ち込む」。落ち込むからさらに「落ち込む」。このままいけばどんどん「落ち込む」・・・・・
その一方で、どういうわけか億万長者が年々増加しているというが、このままその「落ち込み」が延々と連続すればやがてその億万長者にも「落ち込み」が陰るのは真理だろう。
豊かさとは何か・・・・
豊かさとは「おカネ」をたくさん持っていることなのだろうか・・・・・・
使い切れないほどのおカネを、つまり常識を超えたお金を持っていることが「豊かさ」なんだろうか。
本来の「豊かさ」とは、普通の生活をする中にあっては広義な制度としての「社会保障」がなされ、
庶民の生活にあっては、普通の所得で普通の生活ができ将来への希望、夢の持てる、そんな社会ではないだろうか。
大衆はけして大金持ちを羨んだりしたりはしない。分相応を心得る・・・・・・
羨むどころか、その人物に「尊敬の念」さえ抱くものだ。
しかし、今のこの国の社会構造の中での貧富格差、つまり「政策的格差」は国民全体に諦め感さえ醸している。
結局、バブル崩壊以前、「一憶総中流」と言われた、それなりに国民が「中流意識」、つまりみんなが大体同じ生活ができている・・・・・・
そういった安心感から、社会そのものが世界で最も安全で、安心な労働環境の中で勤勉し、将来の夢も語れた。
とくに、過去10年、それは自民党政権下、そんな時代から一変し、労働環境はその4割弱が法改正で制度的に非正規労働を余儀なくされ、
毎日雇用に不安の中ろうどうし、派遣切り、失業、ホームレスといった最悪の社会環境を生んでしまっている。
その中でも、一番の問題は人生のスパンの中で一番おカネのかかる世代の「労働不安」だろう、賃金カット、リストラ、非正規労働者化・・・・・・・
コレではいくらユニクロの駐車場に行列ができてもこの国はお先真っ暗ではないか。2、3年前まではSMを競ったイオン、ヨーカドーに陰りも。コンビニにも陰りが。
豊かさとは何か・・・・
政府は税収不足を言いながら未だ高額所得する富裕層への課税強化には口を紡ぐ。
ソレはなぜか。つまり、政府に属する階層こそが「富裕層」だからである・・・・・・
最高税率の推移。
1986年 70.0%
1987年 60.0%
1989年 50.0%
1999年 37.0%
2007年 40.0%
この数字から見ると07年以降の最高税率40%は86年の1000万円台の水準だ。
近年、率としては高いところに薄く、低いところへ厚く課税する「逆進税」となっており当然消費行動は弱まる。
どうだろう・・・・・・
累進課税が強化されると高額所得者層から不満の声が上がり、労働意欲を殺ぐというが・・・・・
しかし、その高額所得者、富裕層を優遇した結果は「財の停滞」という現象を引き起こし、それは「経済の停滞」につながりデフレを引き起こしている。
つまり、富裕者層の所得に対する消費率は少なくその多くが貯蓄に回る・・・・・・
当然、モノは売れなくなり、それを売れるようにする、商品の「低価格化」、そこでの“企業努力”の大成が「ユニクロ現象」だろう。
結局、この、いわれるデフレ現象を解消し、内需拡大につなげるには、「税制」をいじるしかないのではないか。
それは、ただの累進課税強化ではなく、富裕層が否が応でも消費せざるを得ない課税を執ることだ。
累進課税強化に伴い、つまり、企業にも個人にも大幅に「経費」を消費の使途に認めることだ。
さらに企業の内部留保には課税を強化し、広告宣伝、交際費、設備投資等を、ソレがたとえ中小企業のオッサンのお小遣いであろうと認めちゃう・・・・・・
サラリーマンでも高額所得者にかかわらず、大幅に経費を認める。所得比での一定の金額までは飲食、例えば「おやじ手当て的」なお小遣いの部分も「経費」として認める。
つまり、焼き鳥屋でも領収書をもらって、スナックでも、回転寿司でも、ユニクロの領収書も、ガソリン代もとか・・・・・・
そのかわり、貯蓄、投資への課税は強化する。つまり、最高税率70%でも経費として70%を認める、個人でも法人でもね。早い話が、
「おカネは天下の回りモノ」
で、余ったおカネは政府がお預かりして上手に再配分します。
まあ。信用のおける政府での話ですけど(笑)。しかしそうすれば、相対的に税収は増えるのではないか・・・・・・
多少の時間はかかるかも知れないが、それに消費税での増収には即効性があるから地方財政は見通しが明るくなることは請け合いだ。
大金持ちは高級車を毎年のように買い替え、小金持ちも新製品が出ればすぐにヤマデンに飛び込み。
懐の淋しいお父さんも「やきとりささき」へは週一で通えるかも知れない(笑)。
わが家も、洗濯機が壊れたら修理をせずに、冷蔵庫もいつ買い換えようかと躊躇することなく、嗚呼、液晶の大型テレビも・・・・・・
そう、「エコ減税」なんてぇモノに頼らなくたっていい。しかし一体何なんだあの「エコ減税」は、カネ回りのいいところだけ得させやがって、それにアレは完全に「トヨタ救済策」っていう話じゃあねぇか。
つまりアレは大企業とカネ持ちへの税金の還付でしかない。高速道路休祝日一律1000円も、アレは高速道路利用料金の、一部の利用者への還付だ。
どうせやるなら、全ての利用車両に休祝日「オール1000円均一」解放するべきだ。
まっ、っていうことで所得の再配分が適度に行われ、消費が拡大すれば生産も拡大する。富裕層の否が応でもの消費は低価格品ばかりでなく高価格品の需要にもつながる。
当然その事は「産業の成長」も「経済の成長」も促すことになる。
豊かさとは何か・・・・
それは、経済大国と言われるこの国で、
「普通に生活できる」ことだ。
少なくとも「派遣村」などない・・・・・・

優しくない国は豊かではない Date:2009-09-05
<レビュー引用>
日本は経済大国であるというが豊かな国ではないと著者は言う。何故なら経済力が国民の生活の豊かさには結びついていないから。格差や不公正は拡大し、基本的人権さえ守られていない。勤労者は長い労働時間に疲れきっており、労働の果実は小さく、老後のケアは貧しい。本書は古いと言われ実際書かれたのはかなり昔であるが、告発されている多くの問題は現代にも通じているし、普遍的な問題意識とすら言ってもいい。
物や金の豊かさに没入する事を批判する向きはよくあるものだ。中には豊かさ批判を保守的な価値観の強要やパターナリズムに繋げてしまう人もいるが著者はあくまで多様な生き方、多様な価値観がある事を前提しつつ多様な人々の中にも、社会的にこのような条件があればそれぞれの人が豊かな人生を生きやすくなると考えられる共通の一致点があるはずだ、その共通部分を豊かにすべきではないか、という姿勢をとる。
<以下本文>
09年度の税収は40兆円を下回り、法人税収入は8兆円前後で、ピークだったバブル期、89年度(約19兆円)の半分に満たない水準に落ち込んでいる。
つまり、商売の利益からの税収が落ち込み、所得からの税収も落ち込み、イコール消費も落ち込み消費税収も落ち込む。
なにもかも「落ち込む」。落ち込むからさらに「落ち込む」。このままいけばどんどん「落ち込む」・・・・・
その一方で、どういうわけか億万長者が年々増加しているというが、このままその「落ち込み」が延々と連続すればやがてその億万長者にも「落ち込み」が陰るのは真理だろう。
豊かさとは何か・・・・
豊かさとは「おカネ」をたくさん持っていることなのだろうか・・・・・・
使い切れないほどのおカネを、つまり常識を超えたお金を持っていることが「豊かさ」なんだろうか。
本来の「豊かさ」とは、普通の生活をする中にあっては広義な制度としての「社会保障」がなされ、
庶民の生活にあっては、普通の所得で普通の生活ができ将来への希望、夢の持てる、そんな社会ではないだろうか。
大衆はけして大金持ちを羨んだりしたりはしない。分相応を心得る・・・・・・
羨むどころか、その人物に「尊敬の念」さえ抱くものだ。
しかし、今のこの国の社会構造の中での貧富格差、つまり「政策的格差」は国民全体に諦め感さえ醸している。
結局、バブル崩壊以前、「一憶総中流」と言われた、それなりに国民が「中流意識」、つまりみんなが大体同じ生活ができている・・・・・・
そういった安心感から、社会そのものが世界で最も安全で、安心な労働環境の中で勤勉し、将来の夢も語れた。
とくに、過去10年、それは自民党政権下、そんな時代から一変し、労働環境はその4割弱が法改正で制度的に非正規労働を余儀なくされ、
毎日雇用に不安の中ろうどうし、派遣切り、失業、ホームレスといった最悪の社会環境を生んでしまっている。
その中でも、一番の問題は人生のスパンの中で一番おカネのかかる世代の「労働不安」だろう、賃金カット、リストラ、非正規労働者化・・・・・・・
コレではいくらユニクロの駐車場に行列ができてもこの国はお先真っ暗ではないか。2、3年前まではSMを競ったイオン、ヨーカドーに陰りも。コンビニにも陰りが。
豊かさとは何か・・・・
政府は税収不足を言いながら未だ高額所得する富裕層への課税強化には口を紡ぐ。
ソレはなぜか。つまり、政府に属する階層こそが「富裕層」だからである・・・・・・
最高税率の推移。
1986年 70.0%
1987年 60.0%
1989年 50.0%
1999年 37.0%
2007年 40.0%
この数字から見ると07年以降の最高税率40%は86年の1000万円台の水準だ。
近年、率としては高いところに薄く、低いところへ厚く課税する「逆進税」となっており当然消費行動は弱まる。
どうだろう・・・・・・
累進課税が強化されると高額所得者層から不満の声が上がり、労働意欲を殺ぐというが・・・・・
しかし、その高額所得者、富裕層を優遇した結果は「財の停滞」という現象を引き起こし、それは「経済の停滞」につながりデフレを引き起こしている。
つまり、富裕者層の所得に対する消費率は少なくその多くが貯蓄に回る・・・・・・
当然、モノは売れなくなり、それを売れるようにする、商品の「低価格化」、そこでの“企業努力”の大成が「ユニクロ現象」だろう。
結局、この、いわれるデフレ現象を解消し、内需拡大につなげるには、「税制」をいじるしかないのではないか。
それは、ただの累進課税強化ではなく、富裕層が否が応でも消費せざるを得ない課税を執ることだ。
累進課税強化に伴い、つまり、企業にも個人にも大幅に「経費」を消費の使途に認めることだ。
さらに企業の内部留保には課税を強化し、広告宣伝、交際費、設備投資等を、ソレがたとえ中小企業のオッサンのお小遣いであろうと認めちゃう・・・・・・
サラリーマンでも高額所得者にかかわらず、大幅に経費を認める。所得比での一定の金額までは飲食、例えば「おやじ手当て的」なお小遣いの部分も「経費」として認める。
つまり、焼き鳥屋でも領収書をもらって、スナックでも、回転寿司でも、ユニクロの領収書も、ガソリン代もとか・・・・・・
そのかわり、貯蓄、投資への課税は強化する。つまり、最高税率70%でも経費として70%を認める、個人でも法人でもね。早い話が、
「おカネは天下の回りモノ」
で、余ったおカネは政府がお預かりして上手に再配分します。
まあ。信用のおける政府での話ですけど(笑)。しかしそうすれば、相対的に税収は増えるのではないか・・・・・・
多少の時間はかかるかも知れないが、それに消費税での増収には即効性があるから地方財政は見通しが明るくなることは請け合いだ。
大金持ちは高級車を毎年のように買い替え、小金持ちも新製品が出ればすぐにヤマデンに飛び込み。
懐の淋しいお父さんも「やきとりささき」へは週一で通えるかも知れない(笑)。
わが家も、洗濯機が壊れたら修理をせずに、冷蔵庫もいつ買い換えようかと躊躇することなく、嗚呼、液晶の大型テレビも・・・・・・
そう、「エコ減税」なんてぇモノに頼らなくたっていい。しかし一体何なんだあの「エコ減税」は、カネ回りのいいところだけ得させやがって、それにアレは完全に「トヨタ救済策」っていう話じゃあねぇか。
つまりアレは大企業とカネ持ちへの税金の還付でしかない。高速道路休祝日一律1000円も、アレは高速道路利用料金の、一部の利用者への還付だ。
どうせやるなら、全ての利用車両に休祝日「オール1000円均一」解放するべきだ。
まっ、っていうことで所得の再配分が適度に行われ、消費が拡大すれば生産も拡大する。富裕層の否が応でもの消費は低価格品ばかりでなく高価格品の需要にもつながる。
当然その事は「産業の成長」も「経済の成長」も促すことになる。
豊かさとは何か・・・・
それは、経済大国と言われるこの国で、
「普通に生活できる」ことだ。
少なくとも「派遣村」などない・・・・・・
Posted by 昭和24歳
at 14:58
│Comments(1)
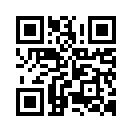


少なくとも「派遣村」などない・・・・・・ <
私もこれが重要だと思います。
しかし、格差騒動で結局、マジョリティに
対するばら撒きに終始する形になりつつ
あります。
しかし、子供がいる家庭まだいいほうで
す、というか育てられないなら・・・という
ことを言っても私は間違いだとは思えま
せんし、そうでなくても孤児が増えている
のは、単に経済的問題とは言い切れな
い部分があると考えております。
2010-11には失業率がどうになるの
か、高卒者の有効求人倍率に至っては
本当なのかと、目を疑います。
投資刺激策として、企業、特に製造業の
減税等を行いないことが、こういうところ
に波及している現実があるのは、しかし、
おそらくそうなってからでないとわからな
いのかもしれません。。
要するに、格差を非とする個人が自分ば
かり不安になり、他者に目が向かなくなり、
もっと格差が増幅するプロセスの一端が
ここにあると思います。