2009年11月04日
浜矩子氏の「ユニクロ栄えて国滅ぶ」
浜矩子氏の「ユニクロ栄えて国滅ぶ」

2009年9月14日 19時43分 ( 2009年9月14日 20時24分更新 )
「ユニクロ栄えて国滅ぶ」 この議論は正しいのか
景気が「底打ち」だとも言われる中、「ユニクロ栄えて国滅ぶ」と題した論文波紋を呼んでいる。快進撃を続けているユニクロなどを例に、「安売りは企業の利益が減り、それが人件費にも跳ね返る。結果、労働者は安いモノしか買えなくなる」などという議論を展開している。もっとも、これにモーレツに反論する経済学者も相次いでいる。
「自分さえ良ければ病」があると指摘
話題を呼んでいるのは、例えば文藝春秋09年10月号に掲載された、エコノミストの浜矩子氏による「ユニクロ栄えて国滅ぶ」と題した論文。価格が下がることで企業の利益が縮小し、それが人件費の切り下げにつながるなどと論じている。
「もっとも、これにモーレツに反論する経済学者も相次いでいる。」
とあるように、その反論をご紹介したい・・・・・・
この過激なまでの安売り競争は、さらに一段の不況地獄の先触れではないだろうか。少し落ち着いて考えてみればいい。250円の弁当で1食すませる生活が当たり前になれば、まともな値段の弁当や食事は「高すぎる」ということになってしまう。
<浜矩子氏の原文>
もう少し落ち着いて考えてみよう。「まともな」値段とは何だろうか。浜氏は原価に「適正利潤」を乗せた価格を想定しているようだが、これは誤りである。少なくとも経済学でいうまともな価格(均衡価格)は、限界費用と等しい水準であり、利潤はゼロになることが効率的なのだ。そういう競争をしたら「経済がどんどん縮小してゆき、デフレの悪循環に陥っていく」と彼女は書くが、そんなことは起こらない。ユニクロや弁当の値下げは貨幣的なデフレではなく、相対価格の変化なので、価格が限界費用と均等化すれば止まる。そして価格が下がれば需要は増えるので、ユニクロのように高い利益が上がる場合も多い。
<池田信夫blogより以下本文>
そこで、池田氏の反論だが・・・・・
・・・・・浜氏は原価に「適正利潤」を乗せた価格を想定しているようだが、これは誤りである。少なくとも経済学でいうまともな価格(均衡価格)は、限界費用と等しい水準であり、利潤はゼロになることが効率的なのだ。そういう競争をしたら「経済がどんどん縮小してゆき、デフレの悪循環に陥っていく」
その浜氏の提言に対し池田氏はこうだ。
そんなことは起こらない。ユニクロや弁当の値下げは貨幣的なデフレではなく、相対価格の変化なので、価格が限界費用と均等化すれば止まる。そして価格が下がれば需要は増えるので、ユニクロのように高い利益が上がる場合も多い。
と言うが、はたしてそうだろうか。池田氏は浜氏をとらえて・・・・・・
「これ以上は説明するのもバカバカしいので、あとは大学1年生の教科書を読んでいただきたい。」
と書くのであえて僕自身を言えば、僕自身「大学1年生」どころか全くの無学モノですので池田氏におかれては埒外の人間でしょうが、浜氏の論文は現実に即して的を得たものと理解したうえで支持します。
そこで、池田氏の言う・・・・・・・
「そんなことは起こらない。」
だが現実には、
「そんなことは起きている」
ことを日常生活の中で実感せざるを得ない思いをしている。
「ユニクロや弁当の値下げが相対価格の変化なので、価格が限界費用と均等化すれば止まる」とかいわれ、「価格が限界費用と均等化」すればということだが、ではいったいいつそれが“均等化”するというのかだろう。
つまり、池田氏の言う「均等化」されるまでに、ユニクロの寡占状況はさらに進み、他の中小商店は市場原理だろうが衰退することになることは必至ではないか。
僕自身、昭和60年からギター製造メーカーとして零細企業の経営にかかわってきたが楽器市場はそのユニクロ以前に価格競争の煽りか、平成8年にその事業を止めた。
そこには「価格が限界費用と均等化」することはなかった。いや、それは池田氏が言うとおりに今日未だ現在進行形なのかもしれないが、その昭和60年から平成8年までの間にその価格競争激化に閉鎖した楽器店も多々あった。
あの、ヤマハ楽器、カワイ楽器ですら軽音部門の店舗閉鎖は半数以上に及んでいる。まあ、楽器業界とユニクロ等衣料業界とはその質を異にするのかも知れませんが、池田氏の言う「ユニクロや弁当の」といわれるようにあながちソレが異なるとも思えない。
つまり、僕らの楽器業界は国内生産から韓国、台湾、そして中国へと移行していったわけだが、その結果、小売り業界での売上はどうなったかといえば・・・・・・
昭和50年代後半から昭和60年代、それまでのギター(エレキ)初心者向け平均価格6万円前後で推移していたモノが今では2万円前後となり、それは総売り上げを相当低下させ経営を圧迫させた結果となった。
まあ、楽器そのものが趣味嗜好のものだから当然市場のパイは決まっているものだが、それだからこそその小さなパイの中での限度を超しての価格競争は市場そのものを衰退させる結果を招いた。
そこで、池田氏の指摘だが・・・・・
問題は要素価格の均等化によって日本の労働者の賃金が中国に鞘寄せされることだが、これは避けられない。IMFによればここ20年、グローバル化とskill-biased technological changeによって所得格差は拡大しており、特に単純労働者の賃金は世界的に均等化している。日本は労働市場が硬直化しているためにその影響は小さかったが、非正社員の増加という形でその影響が出ている。この潮流から自衛するする方法は、基本的には二つしかない。
そこで池田氏は日本の「労働賃金が中国に鞘寄せ」されるがそれは避けられないという・・・・・
しかし「避けられない」では済まないのがこの浜矩子氏の「ユニクロ栄えて国滅ぶ」の本質ではないだろうか。
つまり、日本の労賃が「中国に鞘寄せ」されればされるほど、そのユニクロも「安い」ところから、「高い」に変質してしまいかねない。結局・・・・・・
「250円の弁当で1食すませる生活が当たり前になれば、まともな値段の弁当や食事は「高すぎる」ということになってしまう。」
ということは、その250円はタダの価格競争で、その競争に勝つために他店では220円で売るとかという破滅的な価格競争に陥りイコールそこでの労賃は低下せざるを得ない。
まあ、250円だからと言って一人の人間が2食食えるわけがないわけだから、当然売上は天井を打つことになる・・・・・
「日本は労働市場が硬直化しているためにその影響は小さかったが、非正社員の増加という形でその影響が出ている。この潮流から自衛するする方法は、基本的には二つしかない。」
そこで、「二つしかない」解決策は“池田氏のblog”にリンクしていただくこととして・・・・・・
その「二つしかない」のはその通りなのです。
で、「その通り」まで、日本のそれが持ち堪えられるだろうかということを浜氏の論文は言っているのではないか。
しかし、その「二つしかない」それは政治、政策ではしか解決できないことではないだろうか・・・・・・
「限界生産力説の教えるように、賃金を上げる方法は長期的には労働生産性を上げるしかないのだ。」
「長期的には労働生産性を上げるしかないのだ」
まさしく、政治、政策の範疇ではないか。
つまり浜矩子氏の「ユニクロ栄えて国滅ぶ」は、
そこに至るまでに国民経済が疲弊してしまうのではないかという憂慮であるのではないかと・・・・・・・

2009年9月14日 19時43分 ( 2009年9月14日 20時24分更新 )
「ユニクロ栄えて国滅ぶ」 この議論は正しいのか
景気が「底打ち」だとも言われる中、「ユニクロ栄えて国滅ぶ」と題した論文波紋を呼んでいる。快進撃を続けているユニクロなどを例に、「安売りは企業の利益が減り、それが人件費にも跳ね返る。結果、労働者は安いモノしか買えなくなる」などという議論を展開している。もっとも、これにモーレツに反論する経済学者も相次いでいる。
「自分さえ良ければ病」があると指摘
話題を呼んでいるのは、例えば文藝春秋09年10月号に掲載された、エコノミストの浜矩子氏による「ユニクロ栄えて国滅ぶ」と題した論文。価格が下がることで企業の利益が縮小し、それが人件費の切り下げにつながるなどと論じている。
「もっとも、これにモーレツに反論する経済学者も相次いでいる。」
とあるように、その反論をご紹介したい・・・・・・
この過激なまでの安売り競争は、さらに一段の不況地獄の先触れではないだろうか。少し落ち着いて考えてみればいい。250円の弁当で1食すませる生活が当たり前になれば、まともな値段の弁当や食事は「高すぎる」ということになってしまう。
<浜矩子氏の原文>
もう少し落ち着いて考えてみよう。「まともな」値段とは何だろうか。浜氏は原価に「適正利潤」を乗せた価格を想定しているようだが、これは誤りである。少なくとも経済学でいうまともな価格(均衡価格)は、限界費用と等しい水準であり、利潤はゼロになることが効率的なのだ。そういう競争をしたら「経済がどんどん縮小してゆき、デフレの悪循環に陥っていく」と彼女は書くが、そんなことは起こらない。ユニクロや弁当の値下げは貨幣的なデフレではなく、相対価格の変化なので、価格が限界費用と均等化すれば止まる。そして価格が下がれば需要は増えるので、ユニクロのように高い利益が上がる場合も多い。
<池田信夫blogより以下本文>
そこで、池田氏の反論だが・・・・・
・・・・・浜氏は原価に「適正利潤」を乗せた価格を想定しているようだが、これは誤りである。少なくとも経済学でいうまともな価格(均衡価格)は、限界費用と等しい水準であり、利潤はゼロになることが効率的なのだ。そういう競争をしたら「経済がどんどん縮小してゆき、デフレの悪循環に陥っていく」
その浜氏の提言に対し池田氏はこうだ。
そんなことは起こらない。ユニクロや弁当の値下げは貨幣的なデフレではなく、相対価格の変化なので、価格が限界費用と均等化すれば止まる。そして価格が下がれば需要は増えるので、ユニクロのように高い利益が上がる場合も多い。
と言うが、はたしてそうだろうか。池田氏は浜氏をとらえて・・・・・・
「これ以上は説明するのもバカバカしいので、あとは大学1年生の教科書を読んでいただきたい。」
と書くのであえて僕自身を言えば、僕自身「大学1年生」どころか全くの無学モノですので池田氏におかれては埒外の人間でしょうが、浜氏の論文は現実に即して的を得たものと理解したうえで支持します。
そこで、池田氏の言う・・・・・・・
「そんなことは起こらない。」
だが現実には、
「そんなことは起きている」
ことを日常生活の中で実感せざるを得ない思いをしている。
「ユニクロや弁当の値下げが相対価格の変化なので、価格が限界費用と均等化すれば止まる」とかいわれ、「価格が限界費用と均等化」すればということだが、ではいったいいつそれが“均等化”するというのかだろう。
つまり、池田氏の言う「均等化」されるまでに、ユニクロの寡占状況はさらに進み、他の中小商店は市場原理だろうが衰退することになることは必至ではないか。
僕自身、昭和60年からギター製造メーカーとして零細企業の経営にかかわってきたが楽器市場はそのユニクロ以前に価格競争の煽りか、平成8年にその事業を止めた。
そこには「価格が限界費用と均等化」することはなかった。いや、それは池田氏が言うとおりに今日未だ現在進行形なのかもしれないが、その昭和60年から平成8年までの間にその価格競争激化に閉鎖した楽器店も多々あった。
あの、ヤマハ楽器、カワイ楽器ですら軽音部門の店舗閉鎖は半数以上に及んでいる。まあ、楽器業界とユニクロ等衣料業界とはその質を異にするのかも知れませんが、池田氏の言う「ユニクロや弁当の」といわれるようにあながちソレが異なるとも思えない。
つまり、僕らの楽器業界は国内生産から韓国、台湾、そして中国へと移行していったわけだが、その結果、小売り業界での売上はどうなったかといえば・・・・・・
昭和50年代後半から昭和60年代、それまでのギター(エレキ)初心者向け平均価格6万円前後で推移していたモノが今では2万円前後となり、それは総売り上げを相当低下させ経営を圧迫させた結果となった。
まあ、楽器そのものが趣味嗜好のものだから当然市場のパイは決まっているものだが、それだからこそその小さなパイの中での限度を超しての価格競争は市場そのものを衰退させる結果を招いた。
そこで、池田氏の指摘だが・・・・・
問題は要素価格の均等化によって日本の労働者の賃金が中国に鞘寄せされることだが、これは避けられない。IMFによればここ20年、グローバル化とskill-biased technological changeによって所得格差は拡大しており、特に単純労働者の賃金は世界的に均等化している。日本は労働市場が硬直化しているためにその影響は小さかったが、非正社員の増加という形でその影響が出ている。この潮流から自衛するする方法は、基本的には二つしかない。
そこで池田氏は日本の「労働賃金が中国に鞘寄せ」されるがそれは避けられないという・・・・・
しかし「避けられない」では済まないのがこの浜矩子氏の「ユニクロ栄えて国滅ぶ」の本質ではないだろうか。
つまり、日本の労賃が「中国に鞘寄せ」されればされるほど、そのユニクロも「安い」ところから、「高い」に変質してしまいかねない。結局・・・・・・
「250円の弁当で1食すませる生活が当たり前になれば、まともな値段の弁当や食事は「高すぎる」ということになってしまう。」
ということは、その250円はタダの価格競争で、その競争に勝つために他店では220円で売るとかという破滅的な価格競争に陥りイコールそこでの労賃は低下せざるを得ない。
まあ、250円だからと言って一人の人間が2食食えるわけがないわけだから、当然売上は天井を打つことになる・・・・・
「日本は労働市場が硬直化しているためにその影響は小さかったが、非正社員の増加という形でその影響が出ている。この潮流から自衛するする方法は、基本的には二つしかない。」
そこで、「二つしかない」解決策は“池田氏のblog”にリンクしていただくこととして・・・・・・
その「二つしかない」のはその通りなのです。
で、「その通り」まで、日本のそれが持ち堪えられるだろうかということを浜氏の論文は言っているのではないか。
しかし、その「二つしかない」それは政治、政策ではしか解決できないことではないだろうか・・・・・・
「限界生産力説の教えるように、賃金を上げる方法は長期的には労働生産性を上げるしかないのだ。」
「長期的には労働生産性を上げるしかないのだ」
まさしく、政治、政策の範疇ではないか。
つまり浜矩子氏の「ユニクロ栄えて国滅ぶ」は、
そこに至るまでに国民経済が疲弊してしまうのではないかという憂慮であるのではないかと・・・・・・・
Posted by 昭和24歳
at 10:59
│Comments(4)
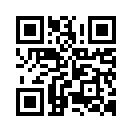


おまけにですが、労働生産性はほぼ
頭打ちです(;¬¬)
さらに、価格が利益=0
で止まるとは必ずしも限りません。
スーパーや料理屋を経営しているか
たならすぐにわかる話です(;¬¬)
デフレは過度な競争を生むことが問
題そのもので、サンクスコストの問題そ
のもの。
そのうえで、限界成長率0である場合
ある場所への投資は別の場所でのサン
クスコストです。
心理的に感じられる豊さっていうのは、
私見ですが、あくまで成長率です(;¬¬)
楽観的な見解を示している気がされま
す。
以前こんな話を聞いたことがあります。
スマイルカーブ、長くなる話ですが、よ
うするにこれです。
産業を選ぶ話ではないわけで、個人
の裁量権が大きいのも事実です。
簡単にいえば、中流、おもに組み立て
を中国が安くこなしてくれるから、上流
と下流にチャンスがあります。
端的には営業と開発です。
結局それらが、中国との競争を避ける、
そのためのスキルである、それが池田
先生のご見解だと思います。
免許や資格のみを指すわけではありま
せん。
経営的な話ではありますが・・・(汁)
池田先生(大作じゃあありません)のそれ(文末の方)は産業構造の変革を言っているのではないでしょうか。
それは「正解」です。その通りになるべきです。
そして、「中国と競争するべきではない」の論も正しい選択ですね。
問題は、そこに至るまでに「中小零細」は絶えてしまうのではないかという現実的な政策問題です。
つまり、それを「淘汰」として看過する政策なのか、それとも政策的に「保護」するのか。かつての池田、佐藤、田中政権ではそうした産業を「保護」した上で貿易政策を取ってきました。
その意味でいえば「ユニクロ問題」は日本政府が求めるべき「逆・繊維交渉」ではないでしょうか。つまり、「ユニクロ」がかつて米国から見た「ニッポン」ということです。
極論かもしれませんが、その意味では「ユニクロ」は「中国産業」であるということです。
さて、本日も問屋町「ユニクロ」の駐車場は満杯、道路沿いは入庫待ちで数珠(笑)。
高崎イオンも「ユニクロ」を核にしないといけないかも知れません(汗)。
処方箋の是非は自明だと思います。
いくら規模の経済が達成されても、
同業同種で喧嘩していてはしょうがな
いのは事実です。
もっと言うと、新規雇用の道という、も
っと具体的な話になっていると思いま
す。
ユニクロが中国産業であるというもの
は極論でもなくて、貿易で輸入するこ
ととは、相手国の要素移転と考えるこ
とが無理なく言えます。
つまりこれは、物を作るのに必要な、
全要素(特に土地、雇用、資本)があた
かも国内に加えられることと同じです。
この場合、国内産業の保護のために
重量課税や、数量割り当てなどの方
法で輸入規制することがあまりにも、
露骨な保護主義であるために、だった
ら人・モノ・金の移動を自由にして、あ
ちらの中流の雇用を国内に移転する
ことが達成されれば、国内所得が増え
るとはGDP成長の取っ掛りになるという
発想だと思います(;¬¬)
購買力平価を考えれば、出稼ぎ労働者
移動の方が明らかに現状では上回る
気もされますが(;¬¬)