2009年04月11日
アイスキャンディー

「ワーーーーーッ!!」
自転車の荷台に水色の・・・・・
所々、塗料の剥げた水色の箱に「アイスキャンディー」と書かれていて。
これまた幟旗にもも水色地に白抜き文字で、
「アイスキャンディー」
と・・・・・・
おじさんが「チリ~ン、チリ~ン」と鐘を鳴らしながらやってくる・・・
あの頃の「アイスキャンディー」はサッカリンを水に溶かしてただ凍らせたやつではなかったか。
夏の「風物」である。
たらたらと、滴り落ちる「アイスキャンディー」の水滴を恨めしく思いつつ、下の方を舐めようとすると・・・・・・
間の悪い時には、上のほうが「ポトリ」と地面に落っこちる。
「あ~っ、俺は何と運の悪い男なんだ」
と、子どもながらに、そう思って儚んだものだった(笑)。
そうだ、おやつと云えば・・・・・
mitukuniさんじゃあないけれど、夏は竹の皮でシソ梅干を包んだやつを、よく作ってもらった。
「これ喰え、腹こわさねえぞ・・・」と父。
後は、茄子の糠づけ・・・口ん中を紫にして、中身を穿り返して・・・・・
いつまでも、いつまでも食いつづけていた。というか干からびるまでしゃぶっていた。
腹が減ると、味噌の握り飯・・・・・
冬は、「ジリ焼き」うどん粉に味噌とかを混ぜてフライパンで焼いたやつ。
母の手が空いているときは、「炭酸」なんかを入れて、ちょいとフックラとさせて・・・・・
でもその炭酸、混ぜ具合が悪いとその炭酸の粉粒の苦いのニガクないのときたらなかった。
ときに「ザラメ」なんかが手に入ると、父が七輪で「カルメ焼き」なんかもしてくれた・・・・・
その時の父の自慢そうな姿が今でも目に浮かぶ。
そうだ、今では、「うどんの手打ち」なんて商売になってるけど、昔は何処ん家も「手打ち」。
僕の家にも、今でもあるが手回しの「うどん作り機」。
どうせ、水団なんか食わされた時は「米びつ」空っぽだったんだろうね。おれんち(笑)。
「突貫豆屋」なんて云うのも来た・・・・・
大豆を持ってくと、煎餅にしてくれるのとか、今で云う「ポン菓子屋」で、
米を2合升ぐらい袋に入れてもってくと「ドカーーーーン」と云う音と共に豆菓子にしてくれるのもあった。
朝は、卵屋と納豆屋の売り声で・・・よく目を覚ましたもんだ。
そう云えば3年生くらいまで、毎日のように寝小便をしていたのが恥ずかしい・・・
終いには、パンツもなくなっちゃって、姉ちゃんのを穿かされたのにはまいった。
まさかその俺が・・・その僕が、還暦だなんて、信じられない。でも事実なのだから仕方が無い・・・・・
そうだ、ゆっくり、マッタリ生きよう・・・・・
未だはもうなり、もうは未だなり・・・
腹を立てずに、計画を立てて。
どうでもいいことだけど・・・僕ら世代は戦後のその貧しさという必然性に育ってきた。
「終戦後」と云う言葉を急いで忘れようとしている大人たちの生活文化の中で。
「駄菓子屋」は、僕ら戦後っ子にとっては一つの食文化だった。
着色料、添加物たっぷりの駄菓子、「ソースイカ」・・・・・・
衛生も糸瓜もないサッカリンたっぷりの「舐め紙」。
そして極めつけの芸術作品でありながらも、小学校の門の前で屋台を開いていた「お新粉細工」屋。
親たちは・・・「腹壊すから・・・」と、呆れていたが、下校時ともなると餓鬼連中(僕等)が・・・・・・
テカテカのお下がりの「詰襟」と下駄に足袋で、「5円玉」握り締めて列をなした。
丁度、配給も終わって、そろそろ米穀台帳なしに米が買える時代・・・・・昭和33年頃か。
焼きそば屋、お新粉細工屋、飴細工屋、針金細工屋・・・・・
学校が終わりになる頃になると日替わりでそんな屋台が校門に店を構えた。
「夜泣きラーメン、食堂」なんて云ったら、盆暮れあるかないかの「御馳走」だったし・・・・・
ご飯だって「竃」、秋刀魚は「七輪」、内風呂なんてある家は当然向こう三軒両隣あるはずもない。
銭湯も老若男女、大衆の社交場。
貧乏比べを笑い飛ばしていた「愉快」なそんな時代だった。
便所は、汲み取り式で、肥溜め屋が野菜の肥料集めに一軒一軒リヤカーに溜め桶をいっぱいにして回ってく。
梅雨近くになると、役所の消毒車(自動車ではない、リアカー)に消毒液噴霧ポンプを積んで、
これまた一軒一軒消毒して周る・・・・・・
蝿帳に蝿取紙、蚊帳に蚊取り線香・・・・・「停電」なんて日常茶飯事。
コンメ(小梅)喰って、腹痛起こして死んじまったり、イボ、ハタケ、タムシ、ハゲ・・・・・
鼻水はたらたら、シモヤケ、アカギレ・・・
今の親が見たら卒倒してしまいそうな健康状態の僕等。
もちろん、よっぽどでなければ「医者」なんて行かない・・・と云うより、当時は殆どが「往診」。
ベーごま、めんこ、が子ども達の経済養成所。
如何にして勝つか、如何にして身上を残すか・・・
「ベーごま」では、持ち駒で一番強いのを「身上丸」と云って財産にしていた。
そんな連中、戦後っ子が、勝負強かったはずなのに今では・・・その「経済」も、落ち目。
恐らく、今、閣僚席、永田町に生息する「霊長類」にはそうした体験、そうした時代的経験は無かったのでは・・・
昔、田名部(青森選挙区)、元農水大臣が云われたとおり、世襲政治家は商売、勝負に経験が無い。
蝶よ花よの坊ちゃん嬢ちゃん。当然、貧乏人とは、庶民大衆とは遊ぶことはまかりならん・・・
子どものうちから、金勘定するなんて品が悪い・・・
もっとも、大人になってから「労働」もせずに「金勘定」ばっかしているのだから、何おか況やだが・・・・・
アイスキャンディーのあのころが懐かしいなぁ。
Posted by 昭和24歳
at 17:46
│Comments(2)
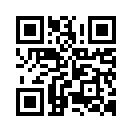


茨城の度田舎だけの話だと思ってました。
親の実家がでんぷん工場だったそうで、水あめが1斗缶ごとあって、水あめだけは食べ放題でした。
昔話は盛り上がるなぁ!
ドドメを竹筒に入れて潰したジュースも飲みました。
椎の実も食べたし、ザリガニも食べました。
タニシもカエルもイナゴもみんな食べました。
夏休み前には必ず、「青い梅は食べてはいけません。」と先生から注意がありました。
アイスキャンデーを食べた後は、必ず棒を折って捨てるようにも言われました。
二度使いをされると、不衛生だからと。