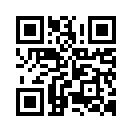2019年11月06日
団塊のエンディングノート(秋に)
団塊のエンディングノート(秋に)

昭和24歳が満一歳の時...
約半数の17社が赤字…地方百貨店は“消滅カウントダウン”に入った
「小売りの主流は郊外にあるショッピングセンターに移っています。地方は特にその傾向が顕著で、駅前立地の百貨店は苦しくなるばかりといえます。この先、どうやって生き残っていくか。打つ手なしの状況といえるかもしれません」(増田和史氏)
売上高の上位20社を見ても前年度を超える売上高を記録したのはタカヤナギ(秋田)、川徳(岩手)、山陽百貨店(兵庫)など7社しかない。群馬県のスズランは2ケタの減収(12・7%)に陥っている(別表参照)。
<抜粋引用:2019年11月06日 09時26分 日刊ゲンダイDIGITAL>
https://news.nifty.com/article/economy/business/12136-457794/
>「この先、どうやって生き残っていくか。打つ手なしの状況といえるかもしれません」
そうだね、生き残り策に打つ手なしですか。
高崎スズランか、前橋スズランかそれがどっちなのかはわからないけど、もしかして両方?
この国の企業もこうなることは分かっていただろうけど、つまり人口減少はときの政策、占領軍の人口戦略ということ。
団塊世代をはさんで戦後の日本の人口規模は一気に2000万人から増加した。
そこで大きく発展したのが流通、消費の拡大だった。つまり高度経済成長、昭和30年から50年のそれ...
その間のインフラ財政投資はその20年間で3兆円からの規模で、ダム、空港、高速道路、新幹線、それらの建設。
ま、ちょうど戦後を脱却した経済成長をそれらへの投資が大きく牽引した。
そして、日本の経済成長がさらに大きく発展するのではないかと思われたその時列島改造論の田中角栄政権はアメリカの手で失脚させられた。それは僕の長女が生まれた年...
実にわかりやすい話で、被占領下、保護領、実質植民地の分際で独自の平和交渉外交、資源外交を果敢に推めようとしたその田中角栄政権。
この時からアメリカの対日戦略はことごとくドルショック、石油ショックをはじめ日本経済の衰退を目論み実践した。
昭和51年(1976年)から20年、日本の政治経済はスキャンダルの嵐で収拾がつかない状態に陥り、結果はバブル経済の発火で西武、国土、国際興業等々、並み居る新興財閥の資産はアメリカの金融資本に奪われた。
日本の資産、日本国有鉄道の解体、日本道路公団、石油公団、住宅公団、そして極めつけは日本電信電話公社、日本郵政の民営化という解体、それら全てがアメリカの対日戦略の中で執り行われ総仕上げが小泉、安倍政権の系譜の中に今日、ジタバタする日本の姿。
この30年ほとんど経済成長していない、賃金は上昇してないどころか下降、それもアメリカの戦略「派遣労働法改正」だった。
小泉純一郎元首相の「人生いろいろ、仕事もいろいろ」。そして「働きたい時働いて遊びたい時、学びたい時学ぶ」...
まあ、そんな都合のいい話があるわけないけど結果「働きたい時働けず、学びたい時学べず、遊びたい時遊べず」といった就職氷河期世代を生み出した。
それは田中角栄が失脚させられた時に生まれた世代にちょうど符合する。今の中年、40代がそれ。
「こうなることは分かっていた」、ということは20年後こうなることは分かっているはずだ。
それを自分の頭で考えて政治に参加することだろう。俺たち団塊はエンディングノートにそう記す(秋に)...
団塊のエンディングノート(秋に)

昭和24歳が満一歳の時...
約半数の17社が赤字…地方百貨店は“消滅カウントダウン”に入った
「小売りの主流は郊外にあるショッピングセンターに移っています。地方は特にその傾向が顕著で、駅前立地の百貨店は苦しくなるばかりといえます。この先、どうやって生き残っていくか。打つ手なしの状況といえるかもしれません」(増田和史氏)
売上高の上位20社を見ても前年度を超える売上高を記録したのはタカヤナギ(秋田)、川徳(岩手)、山陽百貨店(兵庫)など7社しかない。群馬県のスズランは2ケタの減収(12・7%)に陥っている(別表参照)。
<抜粋引用:2019年11月06日 09時26分 日刊ゲンダイDIGITAL>
https://news.nifty.com/article/economy/business/12136-457794/
>「この先、どうやって生き残っていくか。打つ手なしの状況といえるかもしれません」
そうだね、生き残り策に打つ手なしですか。
高崎スズランか、前橋スズランかそれがどっちなのかはわからないけど、もしかして両方?
この国の企業もこうなることは分かっていただろうけど、つまり人口減少はときの政策、占領軍の人口戦略ということ。
団塊世代をはさんで戦後の日本の人口規模は一気に2000万人から増加した。
そこで大きく発展したのが流通、消費の拡大だった。つまり高度経済成長、昭和30年から50年のそれ...
その間のインフラ財政投資はその20年間で3兆円からの規模で、ダム、空港、高速道路、新幹線、それらの建設。
ま、ちょうど戦後を脱却した経済成長をそれらへの投資が大きく牽引した。
そして、日本の経済成長がさらに大きく発展するのではないかと思われたその時列島改造論の田中角栄政権はアメリカの手で失脚させられた。それは僕の長女が生まれた年...
実にわかりやすい話で、被占領下、保護領、実質植民地の分際で独自の平和交渉外交、資源外交を果敢に推めようとしたその田中角栄政権。
この時からアメリカの対日戦略はことごとくドルショック、石油ショックをはじめ日本経済の衰退を目論み実践した。
昭和51年(1976年)から20年、日本の政治経済はスキャンダルの嵐で収拾がつかない状態に陥り、結果はバブル経済の発火で西武、国土、国際興業等々、並み居る新興財閥の資産はアメリカの金融資本に奪われた。
日本の資産、日本国有鉄道の解体、日本道路公団、石油公団、住宅公団、そして極めつけは日本電信電話公社、日本郵政の民営化という解体、それら全てがアメリカの対日戦略の中で執り行われ総仕上げが小泉、安倍政権の系譜の中に今日、ジタバタする日本の姿。
この30年ほとんど経済成長していない、賃金は上昇してないどころか下降、それもアメリカの戦略「派遣労働法改正」だった。
小泉純一郎元首相の「人生いろいろ、仕事もいろいろ」。そして「働きたい時働いて遊びたい時、学びたい時学ぶ」...
まあ、そんな都合のいい話があるわけないけど結果「働きたい時働けず、学びたい時学べず、遊びたい時遊べず」といった就職氷河期世代を生み出した。
それは田中角栄が失脚させられた時に生まれた世代にちょうど符合する。今の中年、40代がそれ。
「こうなることは分かっていた」、ということは20年後こうなることは分かっているはずだ。
それを自分の頭で考えて政治に参加することだろう。俺たち団塊はエンディングノートにそう記す(秋に)...
団塊のエンディングノート(秋に)
Posted by 昭和24歳
at 21:44
│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。