2008年12月27日
チャルメラ横丁
「たかさき」でラーメンを語るには、一時、田町通りに軒を連ねた、「夜鳴き」なくしては後も先もない。
あれは、昭和の三五、六年頃だっただろうか・・・
「来来軒」。

僕の家の傍に住んでいた・・・いや、住んでいたというか、それは「居た」と云う趣であった。
あの時代、それぞれに訳ありのご時世だったし、ご多分に漏れずその来来軒ファミリーもまさにそれそのものだった・・・・・
縦に二畳一間、正真正銘の「うなぎの寝床」の間借。
そんなうなぎの寝床に親子三人で暮らすなんて言うのも別になんとも思わなかった時代だったし・・・・・・
周り中が似たか寄ったかの暮し向きの時代だった。
そのうなぎの寝床の店子の「来来軒」マスターファミリー。
ま、マスターと言ったかどうかは知らないが、そのマスター、なんでも出は良かったようで、高崎の「大店」の「ボン」だったと言う噂はその近所には知れ渡っていた。
来来軒、既に彼岸に旅立ったと風の便りに聞くが・・・その昔、高崎商業高等学校では野球部で腕を鳴らし「甲子園」にも行ったと言う、兵だったらしい。
僕よりも四歳年下の「息子」がその来来軒には居た。
マスターには訳在りの小母さんが時々入替わりに寄せていたが、もちろん「クレイマー・クレイマー」を地で行くような趣であった。
その息子、学校から帰ると健気にも来来軒、親父の「屋台」の支度を手伝い七輪に炭を熾すのも慣れた手つき・・・けして「幸福」とは言ないが、これが滅法明るい横丁の少年だった。
まあ、何処も彼処も似たようなもの、生活環境だったのだから暗くなりようがなかったのだろう。
来来軒のマスターと来た日には、兎に角「酒癖」が悪い。それは「悪い」と言うよりも、多分、酒に「弱い」のではないだろうか・・・〈弱いくせに酒好きで、飲むと人が変わるタイプ〉の人・・・時に良く見かける。
マスター、朝方には、その屋台を枕に酔い潰れている。
「父ちゃん、父ちゃん、風邪ひくよっ」
と、孝行息子。何処までも健気に酔いつぶれた親父を介抱する。
酔っ払った挙句喧嘩でもしたのだろうか、唸りながらブツブツ言ってる来来軒。
「しょうがねえなぁ・・・父ちゃん」
いたわるように呟く息子
「父ちゃん・・・俺、学校、行って来るからね」
と、学校に行く時間になるとそんな孝行息子の優しい声が路地に流れる。
日清製粉の板塀。そこの路地の奥まった所に「来来軒」の屋台はいつも置かれていた。
ある日僕はそんな孝行息子にしばらくぶりに出会った。
「元気ーーー!!」
と、僕に呼びかける無茶苦茶明るい昔の面影を残す来来軒の息子。
その孝行息子も、今度55になると言う。
ラーメンは延びてはいけないが、「幸せ」は延びれば延びるほどよいかも知れない。
その時僕の耳元にあの来来軒の“チャルメラ”がふとよぎった。
♪ピラリーラリ、ピラリラリーラリ♪
来来軒の息子、あの時のままの明るさと満面の笑顔・・・・僕は、その孝行息子にとっておきの元気を貰ったような気がして嬉しくなった。
ふと目を閉じると、日清製粉の板塀と奥まった突付の日清製粉の社宅を背景の来来軒の屋台。
そんな高砂町、横丁の風情に孝行息子の「父ちゃ~~~ん」が聞こえた。
「本郷軒」
江木の方からは「本郷軒」。ここは2代目だと云う。僕は、「たつみ」が良いと言う方も居られるが、なんと云っても「本郷軒」が好みだ。ラーメンの「上がり」が早い。麺はいつも固めで、スープ味はさっぱり目。本当の「支那そば」って云う感じがする。
夕方5時過ぎ頃には「チャルメラ」を鳴らしながら町内を引いていく。先代は歩いて引いたが、2代目は「ホンダスーパーカブ」を、そろりそろりと横丁を往来した。
「ラーメン屋さ~ん」
あちこちからドンブリを手に屋台を囲む。不思議なもので一人が声をかけだすとつられるように四、五人がいつも決まって集まってくる。
当時は未だ「出前」ものを取るとかと言ったような贅沢は無かったし、子供が三、四人もいた日には「ラーメン代」だけでも大変な額になってしまう。
そんな時に決まって声をかけるのはこれから夜のお給仕に出かけるお姉さんかお兄さん。
どちらかと云えば僕等はそれを羨ましそうに眺めていた口であった・・・・・
もちろんそんなお姉さんお兄さんの暮らし向きは貸間住まい。アパートなどと言う代物ではなかったし「バス、トイレ」なんて言う時代ではないので、銭湯帰りだろうか・・・
「兄さん男前ねっ、チャーシュウおまけしてね」
「あいよ」
と、互い、軽口を交わし、柔肌だったかどうかは知らないが得も言えぬ芳香を振りまきながらそのドンブリを手に順番を待っていた。
「本郷軒」は二代目とか言っていた。
そうだ・・・この親爺も「酒好き」の意気地なし(失礼、そう見えた)・・・そして多分「弱い」のだろう。
その本郷軒、朝方は五時頃まで商っている。出掛けにはその途中、横丁の酒屋でコップ酒をすでに軽く一杯引っかけてくる「本郷軒」。車の通りの引けた頃合を見計らって大通りに屋台を張る。夜も更けて九時、十時が食べるなら丁度の時間かもしれない。
「午前様」を迎える頃ともなるとあとはいけない。あとは「へべれけ」で、目を据わらせながら「麺」を上げている。そうなると、折角の「本郷軒」のシコシコ麺もさっぱりスープあったもんじゃあない。
「親爺っ、このラーメン伸びてるぞ」
なんて客が文句のひとつも言おうものならさあ大変。
「なにを…じゃっ、ラーメンもうオシメエだっ。やならよしゃあがれ、ゼニはいらねぇ」
と、言ってさっさと火を落として提灯を消しちゃう本郷軒。
兎に角酒が入るとコロッと変わっちまうのだから始末が悪い。普段はどちらかと云うと物静かなお兄さんなの本郷軒なのだが。このところ、話も聞くことはないが・・・
どうしているだろう。
あれは、昭和の三五、六年頃だっただろうか・・・
「来来軒」。

僕の家の傍に住んでいた・・・いや、住んでいたというか、それは「居た」と云う趣であった。
あの時代、それぞれに訳ありのご時世だったし、ご多分に漏れずその来来軒ファミリーもまさにそれそのものだった・・・・・
縦に二畳一間、正真正銘の「うなぎの寝床」の間借。
そんなうなぎの寝床に親子三人で暮らすなんて言うのも別になんとも思わなかった時代だったし・・・・・・
周り中が似たか寄ったかの暮し向きの時代だった。
そのうなぎの寝床の店子の「来来軒」マスターファミリー。
ま、マスターと言ったかどうかは知らないが、そのマスター、なんでも出は良かったようで、高崎の「大店」の「ボン」だったと言う噂はその近所には知れ渡っていた。
来来軒、既に彼岸に旅立ったと風の便りに聞くが・・・その昔、高崎商業高等学校では野球部で腕を鳴らし「甲子園」にも行ったと言う、兵だったらしい。
僕よりも四歳年下の「息子」がその来来軒には居た。
マスターには訳在りの小母さんが時々入替わりに寄せていたが、もちろん「クレイマー・クレイマー」を地で行くような趣であった。
その息子、学校から帰ると健気にも来来軒、親父の「屋台」の支度を手伝い七輪に炭を熾すのも慣れた手つき・・・けして「幸福」とは言ないが、これが滅法明るい横丁の少年だった。
まあ、何処も彼処も似たようなもの、生活環境だったのだから暗くなりようがなかったのだろう。
来来軒のマスターと来た日には、兎に角「酒癖」が悪い。それは「悪い」と言うよりも、多分、酒に「弱い」のではないだろうか・・・〈弱いくせに酒好きで、飲むと人が変わるタイプ〉の人・・・時に良く見かける。
マスター、朝方には、その屋台を枕に酔い潰れている。
「父ちゃん、父ちゃん、風邪ひくよっ」
と、孝行息子。何処までも健気に酔いつぶれた親父を介抱する。
酔っ払った挙句喧嘩でもしたのだろうか、唸りながらブツブツ言ってる来来軒。
「しょうがねえなぁ・・・父ちゃん」
いたわるように呟く息子
「父ちゃん・・・俺、学校、行って来るからね」
と、学校に行く時間になるとそんな孝行息子の優しい声が路地に流れる。
日清製粉の板塀。そこの路地の奥まった所に「来来軒」の屋台はいつも置かれていた。
ある日僕はそんな孝行息子にしばらくぶりに出会った。
「元気ーーー!!」
と、僕に呼びかける無茶苦茶明るい昔の面影を残す来来軒の息子。
その孝行息子も、今度55になると言う。
ラーメンは延びてはいけないが、「幸せ」は延びれば延びるほどよいかも知れない。
その時僕の耳元にあの来来軒の“チャルメラ”がふとよぎった。
♪ピラリーラリ、ピラリラリーラリ♪
来来軒の息子、あの時のままの明るさと満面の笑顔・・・・僕は、その孝行息子にとっておきの元気を貰ったような気がして嬉しくなった。
ふと目を閉じると、日清製粉の板塀と奥まった突付の日清製粉の社宅を背景の来来軒の屋台。
そんな高砂町、横丁の風情に孝行息子の「父ちゃ~~~ん」が聞こえた。
「本郷軒」
江木の方からは「本郷軒」。ここは2代目だと云う。僕は、「たつみ」が良いと言う方も居られるが、なんと云っても「本郷軒」が好みだ。ラーメンの「上がり」が早い。麺はいつも固めで、スープ味はさっぱり目。本当の「支那そば」って云う感じがする。
夕方5時過ぎ頃には「チャルメラ」を鳴らしながら町内を引いていく。先代は歩いて引いたが、2代目は「ホンダスーパーカブ」を、そろりそろりと横丁を往来した。
「ラーメン屋さ~ん」
あちこちからドンブリを手に屋台を囲む。不思議なもので一人が声をかけだすとつられるように四、五人がいつも決まって集まってくる。
当時は未だ「出前」ものを取るとかと言ったような贅沢は無かったし、子供が三、四人もいた日には「ラーメン代」だけでも大変な額になってしまう。
そんな時に決まって声をかけるのはこれから夜のお給仕に出かけるお姉さんかお兄さん。
どちらかと云えば僕等はそれを羨ましそうに眺めていた口であった・・・・・
もちろんそんなお姉さんお兄さんの暮らし向きは貸間住まい。アパートなどと言う代物ではなかったし「バス、トイレ」なんて言う時代ではないので、銭湯帰りだろうか・・・
「兄さん男前ねっ、チャーシュウおまけしてね」
「あいよ」
と、互い、軽口を交わし、柔肌だったかどうかは知らないが得も言えぬ芳香を振りまきながらそのドンブリを手に順番を待っていた。
「本郷軒」は二代目とか言っていた。
そうだ・・・この親爺も「酒好き」の意気地なし(失礼、そう見えた)・・・そして多分「弱い」のだろう。
その本郷軒、朝方は五時頃まで商っている。出掛けにはその途中、横丁の酒屋でコップ酒をすでに軽く一杯引っかけてくる「本郷軒」。車の通りの引けた頃合を見計らって大通りに屋台を張る。夜も更けて九時、十時が食べるなら丁度の時間かもしれない。
「午前様」を迎える頃ともなるとあとはいけない。あとは「へべれけ」で、目を据わらせながら「麺」を上げている。そうなると、折角の「本郷軒」のシコシコ麺もさっぱりスープあったもんじゃあない。
「親爺っ、このラーメン伸びてるぞ」
なんて客が文句のひとつも言おうものならさあ大変。
「なにを…じゃっ、ラーメンもうオシメエだっ。やならよしゃあがれ、ゼニはいらねぇ」
と、言ってさっさと火を落として提灯を消しちゃう本郷軒。
兎に角酒が入るとコロッと変わっちまうのだから始末が悪い。普段はどちらかと云うと物静かなお兄さんなの本郷軒なのだが。このところ、話も聞くことはないが・・・
どうしているだろう。
Posted by 昭和24歳
at 20:57
│Comments(3)
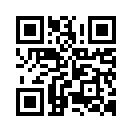


郊外だからなのかなー?
街中はどうなんですか?
昔は、チャルメラの音がすると、自分の家の丼を持って飛び出して行って、そこに入れてもらった記憶があります。
しかし、その“夜泣き”は一軒、未だ頑張っています。二代目だそうですが・・・・・
もちろん毎晩ではありません。毎週金曜日、10時ころから明け方5時ころまで、あら町の赤羽楽器の対面に屋台を広げてます。
亭主もそろそろ還暦じゃあないでしょうか・・・・・
「いつまでつづけられるか?」といいながら凍みる中を頑張っておいでです。
かなり美味いですよ!!
可及的速やかに(お役所っぽい表現ですね)行ってみたいです!