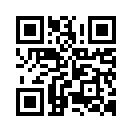2012年01月27日
高砂町「横丁物語」のその後
高砂町「横丁物語」のその後

ノスタルジアをかき立てる写真に昔を思い、現代文明につつしんで疑問を呈する。リンボウ先生の読写真術。
「横丁」。それは今はもうない・・・・・・
昭和の幻影だったのかもしれない「横丁」とか。
日清製粉と東小学校の裏門の入り口からを起点に始まる「高砂町」。
そこは辻違いに弓町、九蔵町、そして高砂町が絡まるようにしている・・・・・
東二条通りと云われているが、そこから北へ3百メートルの所の「五本辻」。
そこが、ほぼ高砂町の中心だがさらに北へ戦前戦中は軍需工場「小島機械」、水島鉄工所があり、
昭和の30年代まではそんな工場群が忙しくしていた。
今では7階建ての市営住宅が建ち、その左手、高崎でも最大規模の染物工場跡には高層マンションが4棟並んでいる。
高砂町。そこは所謂、「職人街」だった。
高崎の近郷近在から高崎へ奉公に出てやがて一人前に仕上がり、独立し。
そして店や細工場、工場を構えた明治後期から大正一桁世代が腕を競い・・・・・・
高砂町を南北に分ける「長野堰」、その西側の末広町まで染物職人忙しそうにしていた。
高砂町一番地はその辻角の「山田畳店」から始まる。
僕が小学生の頃は日清製粉テニスコートを覗く裏辻まで井草の匂いをさせながら工場は細長く畳表を織っていた。
ここに云う、高砂町「横丁物語」はその「山田畳店」から東二条通りを五本辻へ・・・・・・
凡そ、3百メートルの間の表通りと裏通り、路地を描いている。
今ではそこには畳屋の「たの字」も何処にも見えない。
たしかその「山田畳店」、一男三女がいて長男が辻角で「山田歯科医院」を営んでいた。
僕が小学生低学年の頃は大宮の方へ嫁いだ長女の息子が夏休みともなると、ソレ、
「都会」の趣で近所の「ガキ」連中を羨望させていた。
たしか、その親方の孫にあたる少年を「かんちゃん」と呼んで、よく遊んだ。
次女は後に、僕等、東小学校の教師として赴任してくるのだが、「山田先生」と畏怖されていたような記憶がある。
兎に角あの頃の先生は別に山田先生に限らず「怖かった」。
詳細は知らないがその山田歯科医院と軒を並べ、一時だが「一杯飲み屋があった。
そして、その隣も「大塚」さんと云う「赤提灯」。
朝鮮特需でかつての軍需工場「小島機械、水島鉄工所」それと高砂町五本辻の「魚市場」・・・・・・
夕方ともなると三々五々酔客の喧騒が時代を映していた。
高砂町「下」は駄菓子屋が多かった。
その赤提灯と、対面の「安藤自転車店」をおいて、「山盛、長井」と駄菓子屋が2店軒を並べた。並べたと云うよりは、
長屋状態で、安藤自転車、山盛、長井、そして持田鮮魚店と棟続きだったように憶えている。
そうだ、自転車屋の「安藤の浩ちゃん」。何処かで自転車屋の修行をしたかは知らないが、
僕等が物心付く頃には30代そこそこで独立して「オーナー」で威勢がよかった。
山盛の駄菓子屋は、小父さんも小母さんも僕等子供達の間では評判が悪かった。
と云うのも小父さんは模型作りの名人のようで本業は何であったか知らなかったが、
後々に長男が「山盛一平」と云う名前で「看板屋」で結構著名であったことからもその手の有能な職人さんだったようだ。
小母さんは、後妻さんで僕等と同世代の息子、5歳くらい年上の兄貴がいたが、
で、その僕らに評判の悪かった小母さん、晩年は人が変わったように善いお婆ちゃんになり、数年前に葬送した。
駄菓子屋「長井」は冬場は一卓だが、お好み焼なるものもやっていた。
僕より2級上の「明ちゃん」がいた。駄菓子の種類は山盛よりはずっと豊富で、小母さんは愛想もよかった。
やはり、その「長井」で僕等は「駄菓子」の真髄を覚えた。「ソースイカ、ボタンキョウ、サグリ…」何でもあった。
本業は下駄職人、下駄屋であったように記憶する。
長井の前は、道を隔てて「宮崎旗店、山田畳店、有間米穀店」と続く。
宮崎の旗屋は戦中は出征兵士を送る日の丸で随分と栄えたようだが、僕等が子供の頃は、多少の「菓子」を商っていた。
それでも、初刊の「少年マガジン」、35円は、その「宮崎」で買ったような気がするが・・・・・・
それが、山盛だったか、宮崎だったかは断言できない。ただ「長井」でなかったことだけは確かだ。
山田の畳屋。どうして、畳屋には「山田」が多いのか、それともこの辺だけの話なのか?
兎に角、畳屋という畳屋が「山田」。どうやら親戚でもないようなのだがしかし、揃って「山田」なのだ。
今は3代目か。僕等の印象では兎に角畳屋の「セーちゃん」。
背中には彫物があって、猪の首怖そうな「おあ兄さん」だった。
既にその横丁、跡形もない状態だが、隣組で葬儀ともなると積極的に世話を焼いてくれて、兎に角、話が面白い。
酒は一滴もやらないけど下手な酒飲みなんかは軽くいなして、てんで歯が立つどころではない。
終戦後、焼け跡の「ヒロポン」の話から、下ネタ、葬式などで人寄せが始まろうものなら「セーちゃん」オンステージ。
それにしても、可笑しいのが「息子」が跡取なのだが、こうも良く似たものかと思うほどの「一卵性親子」振り。
姿形、出で立ち、話っぷりまでが見まごうばかりの親子。
今日も、軽トラに畳を積んで、高崎の街を流していることだろう。しかし残念ながら「セーちゃん」は数年前に鬼籍に。
昭和40年前後、山田畳店の隣の「有間米穀店」。ここの店先には「ケンタ」、薪束が高く積まれていた。
その脇には、忘れもしない、ダイハツの「ミゼット」が神々しく置かれていた。
有間米穀店は、創業者の小父さんが60そこそこで病に臥し、長男の幸雄ちゃんと新潟から出てきた親戚の「大ちゃん」、
それと、なんと云っても横丁きっての肝っ玉母さんの「小母さん」とで切盛りしていた。
「大」ちゃんはその小母さんの「甥っ子」にあたる・・・・・・・
小母さんも新潟は石地の出で、その絶妙な新潟弁で商いを栄えさせていた。
つづく。
高砂町「横丁物語」のその後

ノスタルジアをかき立てる写真に昔を思い、現代文明につつしんで疑問を呈する。リンボウ先生の読写真術。
「横丁」。それは今はもうない・・・・・・
昭和の幻影だったのかもしれない「横丁」とか。
日清製粉と東小学校の裏門の入り口からを起点に始まる「高砂町」。
そこは辻違いに弓町、九蔵町、そして高砂町が絡まるようにしている・・・・・
東二条通りと云われているが、そこから北へ3百メートルの所の「五本辻」。
そこが、ほぼ高砂町の中心だがさらに北へ戦前戦中は軍需工場「小島機械」、水島鉄工所があり、
昭和の30年代まではそんな工場群が忙しくしていた。
今では7階建ての市営住宅が建ち、その左手、高崎でも最大規模の染物工場跡には高層マンションが4棟並んでいる。
高砂町。そこは所謂、「職人街」だった。
高崎の近郷近在から高崎へ奉公に出てやがて一人前に仕上がり、独立し。
そして店や細工場、工場を構えた明治後期から大正一桁世代が腕を競い・・・・・・
高砂町を南北に分ける「長野堰」、その西側の末広町まで染物職人忙しそうにしていた。
高砂町一番地はその辻角の「山田畳店」から始まる。
僕が小学生の頃は日清製粉テニスコートを覗く裏辻まで井草の匂いをさせながら工場は細長く畳表を織っていた。
ここに云う、高砂町「横丁物語」はその「山田畳店」から東二条通りを五本辻へ・・・・・・
凡そ、3百メートルの間の表通りと裏通り、路地を描いている。
今ではそこには畳屋の「たの字」も何処にも見えない。
たしかその「山田畳店」、一男三女がいて長男が辻角で「山田歯科医院」を営んでいた。
僕が小学生低学年の頃は大宮の方へ嫁いだ長女の息子が夏休みともなると、ソレ、
「都会」の趣で近所の「ガキ」連中を羨望させていた。
たしか、その親方の孫にあたる少年を「かんちゃん」と呼んで、よく遊んだ。
次女は後に、僕等、東小学校の教師として赴任してくるのだが、「山田先生」と畏怖されていたような記憶がある。
兎に角あの頃の先生は別に山田先生に限らず「怖かった」。
詳細は知らないがその山田歯科医院と軒を並べ、一時だが「一杯飲み屋があった。
そして、その隣も「大塚」さんと云う「赤提灯」。
朝鮮特需でかつての軍需工場「小島機械、水島鉄工所」それと高砂町五本辻の「魚市場」・・・・・・
夕方ともなると三々五々酔客の喧騒が時代を映していた。
高砂町「下」は駄菓子屋が多かった。
その赤提灯と、対面の「安藤自転車店」をおいて、「山盛、長井」と駄菓子屋が2店軒を並べた。並べたと云うよりは、
長屋状態で、安藤自転車、山盛、長井、そして持田鮮魚店と棟続きだったように憶えている。
そうだ、自転車屋の「安藤の浩ちゃん」。何処かで自転車屋の修行をしたかは知らないが、
僕等が物心付く頃には30代そこそこで独立して「オーナー」で威勢がよかった。
山盛の駄菓子屋は、小父さんも小母さんも僕等子供達の間では評判が悪かった。
と云うのも小父さんは模型作りの名人のようで本業は何であったか知らなかったが、
後々に長男が「山盛一平」と云う名前で「看板屋」で結構著名であったことからもその手の有能な職人さんだったようだ。
小母さんは、後妻さんで僕等と同世代の息子、5歳くらい年上の兄貴がいたが、
で、その僕らに評判の悪かった小母さん、晩年は人が変わったように善いお婆ちゃんになり、数年前に葬送した。
駄菓子屋「長井」は冬場は一卓だが、お好み焼なるものもやっていた。
僕より2級上の「明ちゃん」がいた。駄菓子の種類は山盛よりはずっと豊富で、小母さんは愛想もよかった。
やはり、その「長井」で僕等は「駄菓子」の真髄を覚えた。「ソースイカ、ボタンキョウ、サグリ…」何でもあった。
本業は下駄職人、下駄屋であったように記憶する。
長井の前は、道を隔てて「宮崎旗店、山田畳店、有間米穀店」と続く。
宮崎の旗屋は戦中は出征兵士を送る日の丸で随分と栄えたようだが、僕等が子供の頃は、多少の「菓子」を商っていた。
それでも、初刊の「少年マガジン」、35円は、その「宮崎」で買ったような気がするが・・・・・・
それが、山盛だったか、宮崎だったかは断言できない。ただ「長井」でなかったことだけは確かだ。
山田の畳屋。どうして、畳屋には「山田」が多いのか、それともこの辺だけの話なのか?
兎に角、畳屋という畳屋が「山田」。どうやら親戚でもないようなのだがしかし、揃って「山田」なのだ。
今は3代目か。僕等の印象では兎に角畳屋の「セーちゃん」。
背中には彫物があって、猪の首怖そうな「おあ兄さん」だった。
既にその横丁、跡形もない状態だが、隣組で葬儀ともなると積極的に世話を焼いてくれて、兎に角、話が面白い。
酒は一滴もやらないけど下手な酒飲みなんかは軽くいなして、てんで歯が立つどころではない。
終戦後、焼け跡の「ヒロポン」の話から、下ネタ、葬式などで人寄せが始まろうものなら「セーちゃん」オンステージ。
それにしても、可笑しいのが「息子」が跡取なのだが、こうも良く似たものかと思うほどの「一卵性親子」振り。
姿形、出で立ち、話っぷりまでが見まごうばかりの親子。
今日も、軽トラに畳を積んで、高崎の街を流していることだろう。しかし残念ながら「セーちゃん」は数年前に鬼籍に。
昭和40年前後、山田畳店の隣の「有間米穀店」。ここの店先には「ケンタ」、薪束が高く積まれていた。
その脇には、忘れもしない、ダイハツの「ミゼット」が神々しく置かれていた。
有間米穀店は、創業者の小父さんが60そこそこで病に臥し、長男の幸雄ちゃんと新潟から出てきた親戚の「大ちゃん」、
それと、なんと云っても横丁きっての肝っ玉母さんの「小母さん」とで切盛りしていた。
「大」ちゃんはその小母さんの「甥っ子」にあたる・・・・・・・
小母さんも新潟は石地の出で、その絶妙な新潟弁で商いを栄えさせていた。
つづく。
高砂町「横丁物語」のその後
Posted by 昭和24歳
at 20:00
│Comments(0)