2010年11月10日
桐生、小6年女子児童自殺Ⅵ
桐生、小6年女子児童自殺Ⅵ

で、「イジメと自殺」の因果関係ですけど・・・・・・
「因果関係」なんてありません。
それ、イジメが「原因」なんですから、「自殺」の。
「いじめ隠さず対応を」小6自殺で文科省通知
読売新聞 11月10日(水)7時17分配信
文部科学省は9日、都道府県教育委員会などに対し、いじめの兆候をいち早く把握して迅速に対応することや、いじめ問題が生じた場合、隠さずに家庭・地域と連携するよう求める通知を、10日に出すことを決めた。
群馬県桐生市の小学6年生、上村明子さん(12)が自殺した問題で、同市教委が「いじめがあった」と認めるまでの間、対応が遅れたことを受けたもので、8日の同市教委の調査結果発表から異例のスピード対応となった。
通知は、上村さんのケースのほか、今年6月に川崎市の市立中学3年の男子生徒(当時14歳)が自殺し、学校でいじめに遭っていた事実が確認されたことにも言及。「いじめはどの学校でも、どの子にも起こりうる」ことを前提に、すべての学校で児童生徒にいじめの有無を聞くアンケートを実施するなど、いじめの実態把握と早期対応の徹底を求めた。
まあ、「イジメ」なんてどこにもあるわけです・・・・・・・
そりゃあ、「文科省」でもあるんじゃない(笑)。
だから、「いじめ隠さず対応を」、いち早くです。
>上村明子さん(12)が自殺した問題で、同市教委が「いじめがあった」と認めるまでの間、対応が遅れたことを受けたもので、
って、市教委がわかるわけありませんし、認めようもありません。
報道では、「担任教諭」は認めていた、ならばおそらくクラスの児童も承知していたこと・・・・・
悪口を言ったり、無視したり、給食を一人で食べていたり、みんな知っていたはず。
校長もその報告は事件後受けていたはず。
だから、「認める、認めない」は感情的な問題ではなく、「教育界」というその閉鎖性からの、
責任回避、「因果関係」がないという強弁がそれを物語っている。
当然、文科省だが、「何を今更」だ。寝ぼけたことを言っていてはイケマセン・・・・・・
そもそも、「イジメ」なんて、コソコソ隠れてやるもんだし、発覚しても、それは知らを切ります。
そしてそれが事件に発展する頃には、その「イジメられっ子」は救われようのないところまでに。
ソノほとんどが集団での「イジメ」ですから、みんなで「やってない」っていうことになれば、
「イジメられっ子」がいくら暗に訴えても無視されるだけです・・・・・・
そしてさらに「イジメ」はエスカレートします。「チクッタ」とかで。
で、もっとひどい場合は、「イジメっ子」は、イジメたくて「イジメられっ子」の家に、仲良しを装って、
迎えに行ったりもします。
そして「仲良し」のフリを見せておいて、また「イジメル」わけです。
子ども社会とはそう言うもんです。まあ、大人社会も似たようなもんですけど・・・・・・
だから、「最悪の事態」だけは何としても回避させる。
それは、それを最初に客観的に認知しえる担任教諭なりがいじめられてる児童の親にその事実を報告し、
登校を中止させるとか、イジメテル、多分集団だろうからその児童の親にその旨を告げる。
おそらく「そんなことは聞いていない」とか言うに決まってるだろうから、そこで毅然と告知する。
まあ、そんなこんなでも、そうしたイジメはなくならない、イジメられっ子れっ子が自殺するまで、イジメはつづく。
つまりそれを前提に対策を講じるわけです・・・・・・
まあ、そんな面倒くさい仕事は嫌でしょうから、でも、そう思う人は教師になってはいけません。
校長になってもいけません、教育委員会委員になってもいけません、文科省の役人になってもいけません。
子ども社会は大人社会以上に「弱肉強食」です。
そこに「理性」を持込み指導をするということはよほどの覚悟と忍耐が求められるわけです。
で、「イジメと自殺」の因果関係ですけど・・・・・・
「因果関係」なんてありません。
それ、イジメが「原因」なんですから、「自殺」の。
桐生、小6年女子児童自殺Ⅵ

で、「イジメと自殺」の因果関係ですけど・・・・・・
「因果関係」なんてありません。
それ、イジメが「原因」なんですから、「自殺」の。
「いじめ隠さず対応を」小6自殺で文科省通知
読売新聞 11月10日(水)7時17分配信
文部科学省は9日、都道府県教育委員会などに対し、いじめの兆候をいち早く把握して迅速に対応することや、いじめ問題が生じた場合、隠さずに家庭・地域と連携するよう求める通知を、10日に出すことを決めた。
群馬県桐生市の小学6年生、上村明子さん(12)が自殺した問題で、同市教委が「いじめがあった」と認めるまでの間、対応が遅れたことを受けたもので、8日の同市教委の調査結果発表から異例のスピード対応となった。
通知は、上村さんのケースのほか、今年6月に川崎市の市立中学3年の男子生徒(当時14歳)が自殺し、学校でいじめに遭っていた事実が確認されたことにも言及。「いじめはどの学校でも、どの子にも起こりうる」ことを前提に、すべての学校で児童生徒にいじめの有無を聞くアンケートを実施するなど、いじめの実態把握と早期対応の徹底を求めた。
まあ、「イジメ」なんてどこにもあるわけです・・・・・・・
そりゃあ、「文科省」でもあるんじゃない(笑)。
だから、「いじめ隠さず対応を」、いち早くです。
>上村明子さん(12)が自殺した問題で、同市教委が「いじめがあった」と認めるまでの間、対応が遅れたことを受けたもので、
って、市教委がわかるわけありませんし、認めようもありません。
報道では、「担任教諭」は認めていた、ならばおそらくクラスの児童も承知していたこと・・・・・
悪口を言ったり、無視したり、給食を一人で食べていたり、みんな知っていたはず。
校長もその報告は事件後受けていたはず。
だから、「認める、認めない」は感情的な問題ではなく、「教育界」というその閉鎖性からの、
責任回避、「因果関係」がないという強弁がそれを物語っている。
当然、文科省だが、「何を今更」だ。寝ぼけたことを言っていてはイケマセン・・・・・・
そもそも、「イジメ」なんて、コソコソ隠れてやるもんだし、発覚しても、それは知らを切ります。
そしてそれが事件に発展する頃には、その「イジメられっ子」は救われようのないところまでに。
ソノほとんどが集団での「イジメ」ですから、みんなで「やってない」っていうことになれば、
「イジメられっ子」がいくら暗に訴えても無視されるだけです・・・・・・
そしてさらに「イジメ」はエスカレートします。「チクッタ」とかで。
で、もっとひどい場合は、「イジメっ子」は、イジメたくて「イジメられっ子」の家に、仲良しを装って、
迎えに行ったりもします。
そして「仲良し」のフリを見せておいて、また「イジメル」わけです。
子ども社会とはそう言うもんです。まあ、大人社会も似たようなもんですけど・・・・・・
だから、「最悪の事態」だけは何としても回避させる。
それは、それを最初に客観的に認知しえる担任教諭なりがいじめられてる児童の親にその事実を報告し、
登校を中止させるとか、イジメテル、多分集団だろうからその児童の親にその旨を告げる。
おそらく「そんなことは聞いていない」とか言うに決まってるだろうから、そこで毅然と告知する。
まあ、そんなこんなでも、そうしたイジメはなくならない、イジメられっ子れっ子が自殺するまで、イジメはつづく。
つまりそれを前提に対策を講じるわけです・・・・・・
まあ、そんな面倒くさい仕事は嫌でしょうから、でも、そう思う人は教師になってはいけません。
校長になってもいけません、教育委員会委員になってもいけません、文科省の役人になってもいけません。
子ども社会は大人社会以上に「弱肉強食」です。
そこに「理性」を持込み指導をするということはよほどの覚悟と忍耐が求められるわけです。
で、「イジメと自殺」の因果関係ですけど・・・・・・
「因果関係」なんてありません。
それ、イジメが「原因」なんですから、「自殺」の。
桐生、小6年女子児童自殺Ⅵ
Posted by 昭和24歳
at 20:28
│Comments(2)
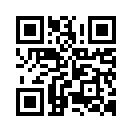


かに教育問題は特殊(そんなにわか
りやすい話しじゃない(汗)
それでもかなり噛み砕くと
教育が公共財であるのは
・非排除性
教育サービスの需要は義務
・非競合性
個別の教科について、ある消費者が
消費しても、それらはなくならないよ
って需給の関係が成立しないから。
そこで需要者のニーズに応じるべき
として義務教育の市場化を実現する
ためのパッケージとして
・教育バウチャー
・学校選択性
・教員免許制
これらを導入して公共性を外すべきと
いうのが昨今の流れ。
これが機能するかどうかは副次的な
問題。
今後ありうるのは学校を淘汰するこ
とによる教育費の削減を目的とした
導入。
教育本来が困るのは教師が意欲をな
くすことらしい。
教育の質には教師の能力、方法論と
いう以上に生徒に対する熱意や愛情
が寄与するらしい。
まさに泥沼…(汗)